埼玉県川口市をホームタウンとするFCアビリスタは、キッズ(未就学児)から中学生まで、幅広い年代の子どもたちを対象として活動しているクラブチームです。トップボトムアップ式指導を取り入れることで、自ら考え実践する人間力とサッカー力の育成を目指すFCアビリスタ。埼玉で長年コーチとしてサッカーに携わってきた鈴木慎一さんが、コーチングの際に大切にしている価値観や、子どもたちへの思いについて語ります。
ダブル・ゴール・コーチングを通してチームの共通理解を深め、価値観のアップデートを目指す
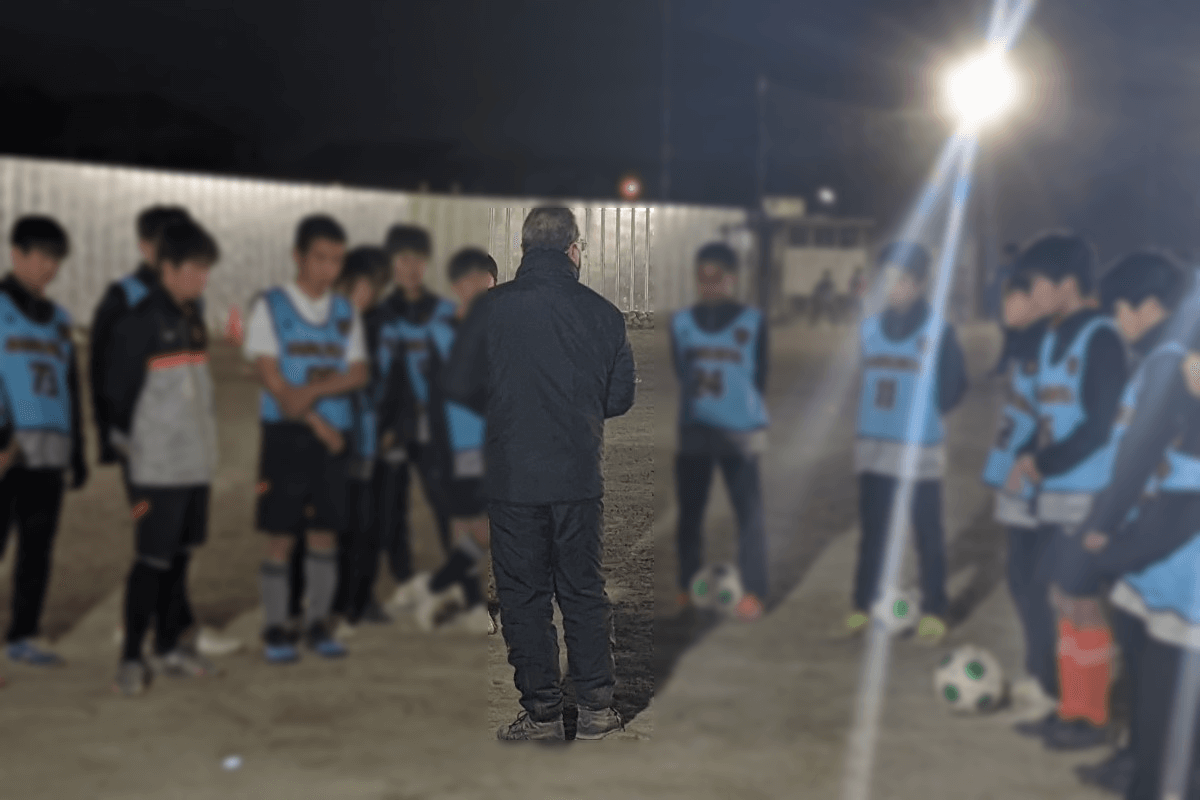
――まずはじめに、FCアビリスタでの鈴木さんの役割について教えてください。
私は、中学生のコーチングスタッフのひとりです。2021年度は、キーパー専門の外部コーチをあわせて、計8名のコーチで3学年を指導しています。3学年をグループ分けして活動するので、時間や場所が別々になることがあるので、このくらいの人数が必要になってくるんですよね。河川敷のような広いグラウンドが確保できればいいんですけど、それがなかなか難しくて。
――ダブル・ゴール・コーチングを学びたいと思ったきっかけがあれば教えてください。
同じチームの今村に勧められたのがきっかけです。ちょうど自分のなかでも『変わらなきゃ』と思っていたタイミングだったので、ありがたかったですね。
――「変わらなきゃ」というのは、具体的にどのような部分で感じていたのでしょうか。
私はほかのコーチよりも年齢が上で、昔ながらの教え込む指導方法がスタンダードだと思っていた時代が長かったんです。しかし、そのやり方を変えなければと感じる場面が年々増えてきました。とはいえ、自分の経験のなかに変わるための術となるベースがほとんどなかったので、海外のコーチングの本を読むところから始めていたときだったんです。
――では、ご自身のなかでも良いタイミングだったのですね。
そうですね。贅沢をいえば、あと5年早く出会いたかったです。それと、先ほどもお話した通り、うちのチームはコーチが複数人います。そうなると当然、指導手法にもそれぞれの色が出てきます。
でも、色の違いが極端だとコーチ間にズレが生じてしまったりして選手も困りますから『共通理解が必要だよね』と以前から今村とは話していたんです。その部分においても、ダブル・ゴール・コーチングというアシストが受けられたことは、チームにとって大きなプラスになっています。
――具体的には、どのような点がプラスになっているのでしょうか。
やはり一番メリットを感じているのは、コーチ同士のコミュニケーションが円滑になったことですね。選手の栄養となる部分の共通理解を深めたいと思っていたので、後藤くん(NPOスポーツコーチング・イニシアチブ チームサポート事業スタッフ)たちが来てくれたタイミングで必要な情報や考え方を共有したり、ときにはリセットしたりできるようになったのは大きいです。
選手だけではなく、コーチングスタッフもひとつのチームとしてまとまっていかなければ良いチームは作れないので。ただ、やはり特効薬ではないので、地道にセッションを積み重ねていくなかでゆっくりと変化していくものだと思います。
新しい風が淀みを払拭してくれた――情報の引き出しを整理し、自分自身を見つめ直す機会を得て

――ダブル・ゴール・コーチングのセッションを受けて、ご自身のなかで変化はありましたか。
ちょうど『変わりたい』と思っていた時期だったんですが、新しい情報が頭のなかで山積みになっていて。本でいえばただ積んでおくだけの状態が続いていたわけです。それがダブル・ゴール・コーチングのセッションを受けることで整理されて、必要なときに必要な知識を取り出せるようになりました。
――自分のなかにある知識を、適材適所で使えるようになったということでしょうか。
そうですね。例えていうなら、工具箱にぐちゃぐちゃに放り込まれていた道具を、後藤くん(NPO法人スポーツコーチング・イニシアチブ チームサポート事業スタッフ)や小林くん(NPO法人スポーツコーチング・イニシアチブ代表)に『この道具を持っているなら、こういう使い方もありますよ』とか『この道具はここに置いておくと使えますよ』と具体的に教えてもらうイメージです。経験から得ていたはずのコーチとして必要な知識や情報も、箱に入れてそのままのものがたくさんありました。
――ダブル・ゴール・コーチングのセッションが、ご自身を見つめ直す機会にもなっているのですね。
自分のなかにあるものを見つめ直す作業って、自分だけだとなかなかうまくいかないんですよね。はるさんも、自分で書いたものを自分だけで校正してもミスを見つけられないってことありませんか。
――めちゃめちゃあります!
何回読み返しても見つけられなかったのに、他人が読み返すとあっさり書き間違いが見つかったりするんですよね。第三者の目が入ることで、チーム内だけでは見つけにくい問題に気づけたりもします。
淀みになっていたところに新しい風が吹くと、底に沈んでいたものが浮かび上がってくることがあるじゃないですか。そういった意味でも、外部の人から指摘や助言をもらえることは、とても有意義だと感じています。
――鈴木さんがコーチングをする際に大切にしている価値観はありますか。
選手と同じ方向で、選手と一緒に進んでいきたいというのが一番にあります。選手たちはやはり『うまくなりたい』『高校サッカー選手権の出場を目指したい』というところを道標としています。
ではそのためには何が必要か、サッカーだけではなく日々の生活の優先順位も含め、選手ごとに伝え方を変えて、ときには個別に時間をとって指導することもあります。
――選手ごとに伝え方を変えるというのは、難しい側面もありそうですね。
とても難しいです。『平等性がない』と見られる場合もあるので。
――そのあたりはどのようにバランスをとっていらっしゃるのでしょうか。
その日の練習メニューや選手の状態によって声がけのボリュームは違ってくるし、限られた練習時間のなかで全員に個別に声をかけることは不可能です。なので、『声をかけられなかったことを不安に思う必要はない』と、年度のはじめにしっかりと伝えるようにしています。
――先にコーチの考えを伝えることで、選手の不安を軽減されているのですね。
自分自身が現役だった頃を思い返してみると、同じような不安は常にありましたから。『練習で何も言われなかったってことは、何も問題なかったってことだよ』とあらかじめ伝えておくことで、選手や保護者は安心できると思うんです。
ほかにも、『あのプレイ良かったよ』『今の判断オッケーだよ』など、目にとまったプレイがあれば、都度声がけをするようにしています。
サッカーを嫌いになる子を作りたくない――チームが合わないと感じたら、いつでも選び直せる環境を

――これまでのコーチ経験を通して、印象深いエピソードがあれば教えてください。
現在ジュニアチームに所属している選手の父兄のなかに、昔の教え子がいるんです。『昔コーチにお世話になりました、○○です』って名刺を渡されて――あれは嬉しかったなぁ。
子どもがサッカーをやりたいって言ったときにここを選んでくれて、しかも向こうから挨拶してくれたっていうのがね。あと、今30歳過ぎになる教え子たちが成人式に呼んでくれたのも感慨深かったですね。
――鈴木コーチと選手との間に信頼関係が育まれていたからこその喜びですね。
こういうことがたまにあると、やっぱりがんばれますよね。町クラブのコーチでも、こんな幸せな思いができるんだなぁって。成功体験が積み重なっていくことが、やりがいにもつながっている気がします。
――子どもたちにとって、どのような環境でスポーツに取り組めるのがベストだと思いますか。
個人的には、選手が自分自身でクラブチームを選べる環境がベストだと思っています。子どもが『やめたい』って言ったときに保護者のほうが熱が入っちゃってやめさせないパターンがけっこうあるんだけど、それだと子どもが潰れてしまうんですよね。それはもったいないなぁ、と。
――望まない場所に留まることを強制されるのは辛いですもんね。
子どもといえども、言ってみれば別の人間の人生ですから。保護者が生きがいにしてしまうのは違いますよね。本人が合わないなと思ったら選び直す。そのほうがストレスなくサッカーを楽しめる気がします。そういう意味では、町クラブがたくさんあるといいですよね、選手の選択肢が広がるので。
――今後、どのようなコーチを目指していきたいですか。
嫌なことは続かないし、好きなことって親の目を盗んでもやるでしょう。そんなふうに、選手とサッカーの関係を前向きなものにできたらいいなと思っています。サッカーを嫌いになる子を作りたくないんです。
コーチと選手の関わりは、あくまでも選手が成長するためのきっかけのひとつであり、『コーチと選手の力関係は対等である』という基本的なところを忘れずにいたいですね。こちらで先回りして用意していたことが選手によってはフィットしないケースもあるので、できるだけ引き出しを増やしておくのが目標です。
コーチを続けるうえで必要なのは、「自身の経験・新しい情報・将来の展望」の3つだと鈴木さんは語ります。どんな情報でも一度は取り入れ、栄養にするかどうするかはそのあとで考える――そんな柔軟な姿勢を持つ鈴木さんは、子どもたちの健やかな成長を願い、自身をアップデートし続けます。目線の先にあるのは、サッカーが好きでたまらない子どもたちの笑顔。教え子たちとサッカーの関係がベストパートナーになれるよう、今日も鈴木コーチは子どもたちと真剣に向き合い、日々の活動に取り組んでいます。
サッカーに携わるコーチや保護者に捧げる~プレーヤーが試合でも人生でも勝者となるコーチング~
スポーツコーチ同士の学びの場『ダブル・ゴール・コーチングセッション』

NPO法人スポーツコーチング・イニシアチブではこれまで、長年スポーツコーチの学びの場を提供してきました。この中で、スポーツコーチ同士の対話が持つパワーを目の当たりにし、お互いに学び合うことの素晴らしさを経験しています。
答えの無いスポーツコーチの葛藤について、さまざまな対話を重ねながら現場に持ち帰るヒントを得られる場にしたいと考えています。
主なテーマとしては、子ども・選手の『勝利』と『人間的成長』の両立を目指したダブル・ゴール・コーチングをベースとしながら、さまざまな競技の指導者が集まり対話をしたいと考えています。
開催頻度は毎週開催しておりますので、ご興味がある方は下記ボタンから詳しい内容をチェックしてみてください。
ダブル・ゴール・コーチングに関する書籍
NPO法人スポーツコーチング・イニシアチブでは、子ども・選手の『勝利と人間的成長の両立』を目指したダブル・ゴールの実現に向けて日々活動しています。
このダブル・ゴールという考え方は、米NPO法人Positive Coaching Allianceが提唱しており、アメリカのユーススポーツのスタンダードそのものを変革したとされています。
このダブル・ゴールコーチングの書籍は、日本語で出版されている2冊の本があります。
エッセンシャル版書籍『ダブル・ゴール・コーチングの持つパワー』

序文 フィル・ジャクソン
第1章:コーチとして次の世代に引き継ぐもの
第2章:ダブル・ゴール・コーチ®
第3章:熟達達成のためのELMツリーを用いたコーチング
第4章:熟達達成のためのELMツリー実践ツールキット
第5章:スポーツ選手の感情タンク
第6章:感情タンク実践ツールキット
第7章:スポーツマンシップの先にあるもの:試合への敬意
第8章:試合への敬意の実践ツールキット
第9章:ダブル・ゴール・コーチのためのケーススタディ(10選)
第10章:コーチとして次の世代に引き継ぐものを再考する
本格版書籍『ダブル・ゴール・コーチ(東洋館出版社)』

元ラグビー日本代表主将、廣瀬俊朗氏絶賛! 。勝つことを目指しつつ、スポーツを通じて人生の教訓や健やかな人格形成のために必要なことを教えるために、何をどうすればよいのかを解説する。全米で絶賛されたユーススポーツコーチングの教科書、待望の邦訳!
子どもの頃に始めたスポーツ。大好きだったその競技を、親やコーチの厳しい指導に嫌気がさして辞めてしまう子がいる。あまりにも勝利を優先させるコーチの指導は、ときとして子どもにその競技そのものを嫌いにさせてしまうことがある。それはあまりにも悲しい出来事だ。
一方で、コーチの指導法一つで、スポーツだけでなく人生においても大きな糧になる素晴らしい体験もできる。本書はスポーツのみならず、人生の勝者を育てるためにはどうすればいいのかを詳述した本である。
ユーススポーツにおける課題に関する書籍『スポーツの世界から暴力をなくす30の方法』

バレーが嫌いだったけれど、バレーがなければ成長できなかった。だからこそスポーツを本気で変えたい。暴力暴言なしでも絶対強くなれる。「監督が怒ってはいけない大会」代表理事・益子直美)
ーーーーー
数えきれないほど叩かれました。
集合の際に呼ばれて、みんなの目の前で顔を。
血が出てたんですけれど、監督が殴るのは止まらなかった……
(ヒューマン・ライツ・ウォッチのアンケートから)
・殴る、はたく、蹴る、物でたたく
・過剰な食事の強要、水や食事の制限
・罰としての行き過ぎたトレーニング
・罰としての短髪、坊主頭
・上級生からの暴力·暴言
・性虐待
・暴言
暴力は、一種の指導方法として日本のスポーツ界に深く根付いている。
日本の悪しき危険な慣習をなくし、子どもの権利・安全・健康をまもる社会のしくみ・方法を、子どものスポーツ指導に関わる第一線の執筆陣が提案します。





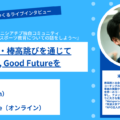


















コメントを残す