スポーツに一定期間取り組んでいると、ある時期に「伸び悩む」経験をすることは多いでしょう。この伸び悩んでいる時期は成長の実感が感じられず、イライラしてしまいがちです。これまで楽しんでいたスポーツや練習に対するモチベーションも落ちてしまいます。
伸び悩んでいる選手を見ているのは、指導者としてももどかしいものでしょう。
伸び悩んでいる選手に対して何とか状況を打破できるようにアプローチしても、功を奏しなかった経験もお持ちだと思います。
伸び悩んでいる状態は、プラトー(高原状態)とも言われ、スポーツ心理学、運動学習、教育心理学などではプラトーについてあらゆる角度から研究されています。
本記事では、スポーツ心理学と教育心理学で使われている限界的練習(deliberate practice)を参考にして、伸び悩み(プラトー)を打破するアイディアを紹介していきます。
プラトーは取り組んでいる練習の効果が得られなくなった状態

伸び悩んでいる状況で考えられるのは、「練習する目標があいまいなまま同じ練習をずっと繰り返している」ことです。
スポーツスキルを身に付けるためには、一定量の反復練習は欠かせません。
ですが、同じ練習をずっと繰り返していればその練習をすることが簡単になってしまい、「もうこの練習から得られることは何もない」という感覚になってしまいます。
一方で、同じ練習をしていても具体的にフォーカスするポイントがはっきりしていれば、その練習を通して何かを学ぶことができます。
しかし、練習に対する目標が曖昧だと、その日の練習で上達したかどうかをはっきりと自覚することが難しくなってしまいます。
加えて、目標が曖昧だとただ何となくやる練習になりがちで、練習中の集中力も低下してしまいがちです。
そのような状態で練習に対するモチベーションを高めるのが難しいのは、想像するに難しくないと思います。
その結果、ますます練習で成長することができなくなってしまい伸び悩む状態(プラトー)になってしまいます。
限界的練習(deliberate practice)はエキスパートになる為の練習システム

限界的練習(deliberate practice)はその道のエキスパートと呼ばれる人たちが行なっていた練習方法をコンセプトとしてまとめたものです(K. A. Ericsson, Krampe, & Tesch-Römer, 1993)。
このコンセプトは、アンダース・エリクソン博士がエキスパートと呼ばれる人たちの練習方法や上達のプロセスについて研究を積み重ねて導き出されたものです。
エキスパートになった人たちに共通して見られたのは、日々の練習の中に成長し続けられるために必要な取り組みが多く取り入れられていたことです。
このエキスパートの共通点をコンセプトとしてまとめ上げたのが限界的練習です。下記の5つがエキスパートの共通点をまとめたコンセプトです (A. Ericsson & Pool, 2016)。
- 学びたいスキルに精通している指導者の元で学ぶ
- 具体的かつ詳細な目標を立てて、その目標を達成していくプロセスを経て成長していく。
- 目標達成の取り組みに対してフィードバックを得て、次への取り組みでは改善された(前回とは違った)取り組みをする。
- 練習中は高い集中力を持って、自分の限界の少し先を目指すようにチャンジする。
- 詳細かつバラエティ豊かな心的イメージを作り上げていく。
この限界的練習のコンセプトの中には、伸び悩み(プラトー)を打破する為に参考になるアイディアがいくつかあります。
特に上記の3番目と4番目が伸び悩み(プラトー)打破に役に立つアイディアが多く含まれています。
ここからは、それらのコンセプトに基づいた取り組みも織り交ぜて、伸び悩み(プラトー)を解決するための方法を紹介していきます。
伸び悩み(プラトー)打破のための限界的練習①負荷を上げる
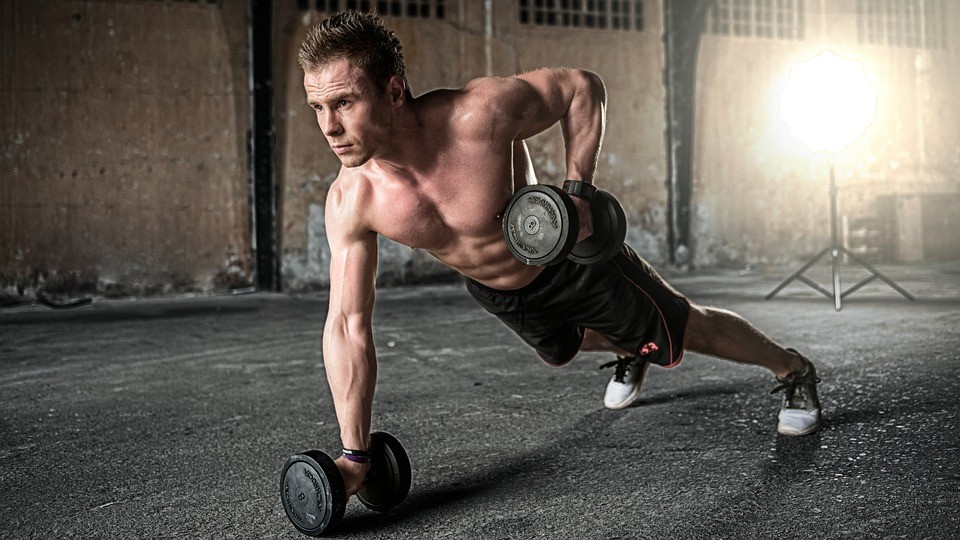
多くの人が既に試していると思いますが、今まで試したことのない方法を試すことで伸び悩み(プラトー)を打破できる可能性が高まります。
ですが、闇雲に選ぶよりも練習しているスキルに似ている別のスポーツを参考にした方が新しいヒントを得られるチャンスは多くあります。
そして、新しいことにトライはしつつも練習の負荷は落とさないことです。
エリクソン博士の短期記憶に関する研究に参加していた青年を例に説明してみます。
その青年がエリクソン博士の研究に参加した当初は、順調に暗記できるケタ数を伸ばしていました。ところが、どうしてもケタ数を伸ばせない時期に直面しました。
その時に彼が行なったのは、これまでと違った暗記方法を試しつつ暗記するケタ数は減らさないようにすることでした。
彼は陸上選手で自分が走るタイムを覚えることに慣れていました。
そこで、覚える数字をタイムに見立てて覚えるようにしたところ、伸び悩み(プラトー)を打破して飛躍的に覚えられるケタ数を伸ばしていきました。
この例は数字の暗記ですが、スポーツのスキルでも同様のことが言えることをエリクソン博士は研究を通して説明しています。
ポイントは、自分に馴染みがある・得意な事柄に関連させて、学んでいる内容(スポーツのスキル)に対する理解を深めることです。
伸び悩み(プラトー)打破のための限界的練習②他種目のスキルを取り入れる

今まで試したことの無い別のスポーツのスキルを試す際には、ある程度似ている動きの物を試すことで伸び悩み(プラトー)打破のヒントをつかめる可能性が高まります。
例えば、バドミントンのスマッシュ、野球の投球動作、バレーボールのスパイクには、それぞれ似た体の動きが見られます。
卓球のバックハンドの手首のしなりは、フリスビーを投げる時の手首の使い方にも似ています。
一方で、関連があまり見られない動きからもヒントを掴む機会も少なくありません。
この点に関しては、過去のスポーツや運動経験が影響してくるため、どのような動きを参考にすればいいかは人によって大きく変わります。
ある程度手探りでの作業になりますが、それでも一貫して言える伸び悩み(プラトー)打破のポイントは「新しい動きや練習を試すこと」です。
伸び悩み(プラトー)打破のための限界的練習③原因を自己分析

伸び悩んでいる時(プラトー状態の時)にやってしまいがちなのが、練習量をやみくもに増やしてしまうことですが、これは効果的なアプローチとは言い難いです。
そもそも、反復練習の目的は「動作を無意識に近い状態で行えるようにすること」です。
その為、正しい動きを覚えていない状態で反復することで却って正しくない動きを体に覚え込ませてしまいます。
それよりも、一度立ち止まって自分の練習中のパフォーマンスを色んな角度から分析して見ましょう。
あらゆる角度から詳しく分析することによって、パフォーマンスを改善する為の具体的な取り組みが見つかります。
具体的な取り組みを見つける上で有効なのは、自分のパフォーマンスをビデオで分析することです。
自分がパフォーマンスしている時の感覚と実際の動きには大きなギャップがある場合が多いです。
映像を通して自分のパフォーマンスを分析してみると、自分ではできていたと思い込んでいた部分が、実は思ったほど良くなかったと感じることはよくあります。
この気づきや発見を基に、伸び悩み(プラトー)打破のための新しい取り組みを考えることができます。
伸び悩み(プラトー)打破のための限界的練習④目標設定をする

映像分析を詳しく行い、伸び悩み(プラトー)を打破する上で重要なのは、練習しているスキルを伸ばすための具体的な目標(取り組み)があることです。
具体的な目標があると練習の進展を確認することができるので、映像を見るポイントが絞りやすくなるメリットがあります。
例えば、卓球のバックハンドに難があるので、「ボールに回転をかけられるように、手首の効かせて打つ」という目標を立てるとします。
この目標のように、見る時に基準になるポイントがあることで、手首を使えるようにするための練習でどの程度上達したかを確認することもできます。 (D’Innocenzo, Gonzalez, Williams, & Bishop, 2016)。
また具体的な目標が定まると、「これをやればいい」と取り組むべきことが明確になり、集中しやすい状況も生まれます。
まとめ
プラトーと呼ばれる伸び悩みの状態は、練習の効果が得られなくなっている状態です。
伸び悩み(プラトー)は、具体的な目標を持たずに同じ練習をずっと繰り返している結果として起こることが考えられます。
その伸び悩み(プラトー)を打破するには、限界的練習のコンセプトである「具体的な目標に対する練習状況を確認して、その都度練習内容を改善していくこと」と「高い集中力で練習に臨み、常に限界の一歩先を目指すこと」がヒントになります。
他のスポーツや似ている動きを参考にして、これまでの練習とは違うやり方を試して見ましょう。
練習中に心がける内容を具体的にすることで、集中しやすい環境を作り出せます。
具体的な目標があることによって、客観的に動きを分析する時に自分の進展具合を確認することができます。
今回ご紹介したアイディア伸び悩んでいる選手の皆さんの解決のヒントになったり、指導している選手が伸び悩み(プラトー)を打破するきっかけになれば、これ以上嬉しいことはありません。
参考文献
D’Innocenzo, G., Gonzalez, C. C., Williams, A. M., & Bishop, D. T. (2016). Looking to learn: the effects of visual guidance on observational learning of the golf swing. PloS one, 11(5), e0155442.
Ericsson, A., & Pool, R. (2016). Peak: Secrets from the new science of expertise. : Houghton Mifflin Harcourt.
Ericsson, K. A., Krampe, R., & Tesch-Römer, C. (1993). The role of deliberate practice in the acquisition of expert performance. Psychological Review, 100(3), 363–406.
スポーツコーチ同士の学びの場『ダブル・ゴール・コーチングセッション』

NPO法人スポーツコーチング・イニシアチブではこれまで、長年スポーツコーチの学びの場を提供してきました。この中で、スポーツコーチ同士の対話が持つパワーを目の当たりにし、お互いに学び合うことの素晴らしさを経験しています。
答えの無いスポーツコーチの葛藤について、さまざまな対話を重ねながら現場に持ち帰るヒントを得られる場にしたいと考えています。
主なテーマとしては、子ども・選手の『勝利』と『人間的成長』の両立を目指したダブル・ゴール・コーチングをベースとしながら、さまざまな競技の指導者が集まり対話をしたいと考えています。
開催頻度は毎週開催しておりますので、ご興味がある方は下記ボタンから詳しい内容をチェックしてみてください。
ダブル・ゴール・コーチングに関する書籍
NPO法人スポーツコーチング・イニシアチブでは、子ども・選手の『勝利と人間的成長の両立』を目指したダブル・ゴールの実現に向けて日々活動しています。
このダブル・ゴールという考え方は、米NPO法人Positive Coaching Allianceが提唱しており、アメリカのユーススポーツのスタンダードそのものを変革したとされています。
このダブル・ゴールコーチングの書籍は、日本語で出版されている2冊の本があります。
エッセンシャル版書籍『ダブル・ゴール・コーチングの持つパワー』

序文 フィル・ジャクソン
第1章:コーチとして次の世代に引き継ぐもの
第2章:ダブル・ゴール・コーチ®
第3章:熟達達成のためのELMツリーを用いたコーチング
第4章:熟達達成のためのELMツリー実践ツールキット
第5章:スポーツ選手の感情タンク
第6章:感情タンク実践ツールキット
第7章:スポーツマンシップの先にあるもの:試合への敬意
第8章:試合への敬意の実践ツールキット
第9章:ダブル・ゴール・コーチのためのケーススタディ(10選)
第10章:コーチとして次の世代に引き継ぐものを再考する
本格版書籍『ダブル・ゴール・コーチ(東洋館出版社)』

元ラグビー日本代表主将、廣瀬俊朗氏絶賛! 。勝つことを目指しつつ、スポーツを通じて人生の教訓や健やかな人格形成のために必要なことを教えるために、何をどうすればよいのかを解説する。全米で絶賛されたユーススポーツコーチングの教科書、待望の邦訳!
子どもの頃に始めたスポーツ。大好きだったその競技を、親やコーチの厳しい指導に嫌気がさして辞めてしまう子がいる。あまりにも勝利を優先させるコーチの指導は、ときとして子どもにその競技そのものを嫌いにさせてしまうことがある。それはあまりにも悲しい出来事だ。
一方で、コーチの指導法一つで、スポーツだけでなく人生においても大きな糧になる素晴らしい体験もできる。本書はスポーツのみならず、人生の勝者を育てるためにはどうすればいいのかを詳述した本である。
ユーススポーツにおける課題に関する書籍『スポーツの世界から暴力をなくす30の方法』

バレーが嫌いだったけれど、バレーがなければ成長できなかった。だからこそスポーツを本気で変えたい。暴力暴言なしでも絶対強くなれる。「監督が怒ってはいけない大会」代表理事・益子直美)
ーーーーー
数えきれないほど叩かれました。
集合の際に呼ばれて、みんなの目の前で顔を。
血が出てたんですけれど、監督が殴るのは止まらなかった……
(ヒューマン・ライツ・ウォッチのアンケートから)
・殴る、はたく、蹴る、物でたたく
・過剰な食事の強要、水や食事の制限
・罰としての行き過ぎたトレーニング
・罰としての短髪、坊主頭
・上級生からの暴力·暴言
・性虐待
・暴言
暴力は、一種の指導方法として日本のスポーツ界に深く根付いている。
日本の悪しき危険な慣習をなくし、子どもの権利・安全・健康をまもる社会のしくみ・方法を、子どものスポーツ指導に関わる第一線の執筆陣が提案します。
























コメントを残す