スキルと能力の違いについて詳しく求められたときに、違いが分からず戸惑ってしまう方は少なくありません。特に転職や企業などに携わるビジネスパーソンであれば、意味の違いを把握してスキルや能力を高めるは大切でしょう。
本記事では、このようなスキルと能力の違いや、高め方について詳しく解説します。
能力とスキルの違いはパラメータかノウハウか
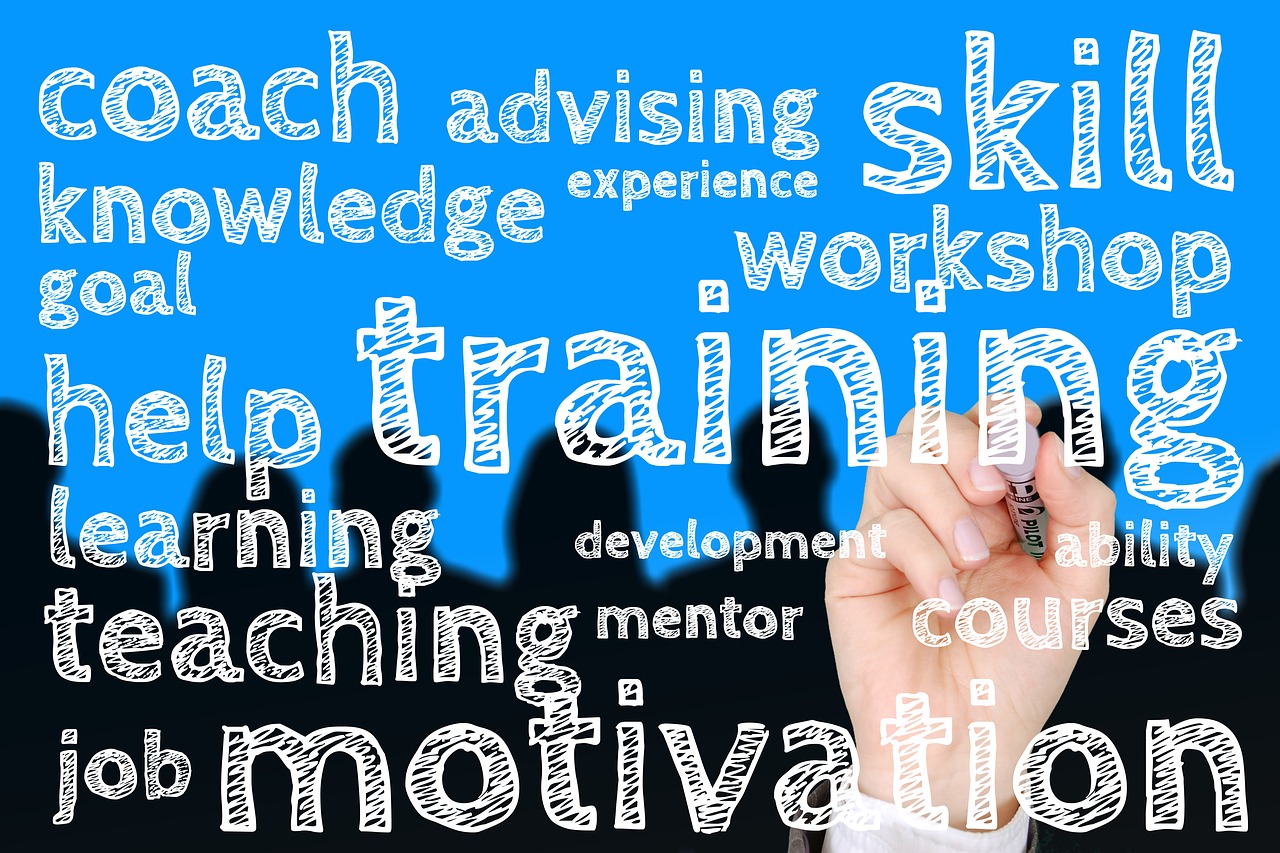
能力とスキルの違いは、パラメータかノウハウかにあります。能力はビジネスパーソン自身がもつ力のことで、能力は多くのスキルを持つことによって高まります。
スキルと能力の違いについては下記の通りです。
能力は英語でAbility
能力は英語でAbilityです。このAbilityは英英辞典で検索すると、”someone’s level of skill at doing something” 1)と記載されています。
解釈としては、スキルよりもすこし抽象的な概念であることが分かります。つまり、スキルがいくつかあったとすると、まとめて「能力」として解釈されます。
スキルは英語でA particular ability
能力に対してスキルは、”A particular ability” 1)と表現されます。つまり特定の能力と解釈されるため、能力(Ability)の一部分をスキルが担っているということです。
スキルがあるから能力が高まる
スキルと能力についてまとめると、いくつか「スキル」が合わさると「能力」になります。言い換えれば、「能力」はパラメータのようなものであり、「スキル」は能力の一部分と言えるでしょう。
能力を高めるためにはマインドセットと業界共通の能力(パラメータ)が重要

能力を高めるためには、物の考え方・捉え方の部分であるマインドセットと、どの業界にも共通しているスキルが重要です。
能力を高めるためのマインドセットは成長マインドセット
能力を高めるためのマインドセットとして、成長マインドセットが挙げられます。この成長マインドセットとは、「自分自身の能力は、努力や経験によって開発できる。」という思考方法です。
マインドセットに関する記事は下記に触れてあるので参考にしてみてください。
この成長マインドセットを持つビジネスパーソンは、どの分野においても自分自身の能力につなげることができます。
例えばエンジニアのビジネスパーソンを対象とした研究結果2)によれば、既に技術を身につけたエンジニアと、エンジニアに関する勉強をしている学生の間には、マインドセットに科学的な違いがあることが報告されています。
つまりこの成長マインドセットは、技術を身につける中で培われやすく、成長マインドセットを持つことができれば、どの能力を高めるにしても高めやすくなるということです。
企業に対して自己PRをする場合には、成長マインドセットの部分をアピールすることで、能力を身につけるマインドが備わっているとみなされるでしょう。
業界共通のスキルとはソーシャルスキルを指す
業界共通のスキルとして、ソーシャルスキルが挙げられます。
能力を高める上では、どの業界においても共通するスキルが重要です。代表的な例としてはコミュニケーションスキルが挙げられます。
このようなコミュニケーションスキルは、ソーシャルスキルとして心理学領域で多くの研究が行われています。
ソーシャルスキルに関して井芹3)は、ソーシャルスキルが社会的資質・能力として位置づけられていると述べています。
このソーシャルスキルの中には、コミュニケーションスキルやリーダーシップスキル、論理的思考力や自己管理能力といった様々なスキルが含まれています。
つまり、どの業界においても基盤となる能力としてソーシャルスキルがあり、ソーシャルスキルを多く持ち合わせているほど業界共通の能力(社会人基礎力など)が高いといえます。
転職活動などで企業に能力を自己PRする場合には、今まで身につけた専門性をPRするのもよいですが、ソーシャルスキルも同様にアピールすることで、社会人としての基礎力が備わっているという印象を与えられるでしょう。
ソーシャルスキルについては下記の記事を参考にしてみてください。
成長マインドセットを養うための思考方法

成長マインドセットを養うための思考方法としては、ポジティブシンキングスキルを高めることは有効ですが、ポジティブシンキングスキルを高める上では、近年ACT(Acceptance & Commitment Therapy)が心理学領域では注目されています。
ACTとは、ポジティブ心理学領域のマインドフルネスなどから派生したとされており、「今の自分自身を受け入れる」ことから始まります。従来の方法として、ネガティブな捉え方をポジティブに捉えるという積極的思考法が主流でした。
積極的思考法のやり方
積極的思考法は、何かネガティブなことが起こった時にポジティブに変換します。
例えば、「仕事でミスをしてしまった、ダメだな、自分」というネガティブな気持ちでいるのではなく、「仕事でミスをしてしまった。でも次ここをこうすればうまくいく」と自分の中で捉え方を変えるような方法です。
この積極的思考法は、日常的に行う事で自分自身の物事の捉え方が自然とポジティブになるように変化させるやり方です。
ACTで成長マインドセットを養って能力を培う
ACTの手法では、「仕事でミスをしてしまった、だめだな、自分」という今の自分自身を受け入れることが重要です。
そのうえで、どういった選択をしてどのような行動をするのかを決めます。
例えば、仕事でミスをして落ち込んでしまっている自分がいて「自分はネガティブに考えてしまっているな、これでは次につながらない。次に同じことをするときにどうしたら上手くいくかな。」と、次のプランニングをする選択をしたとします。
もしプランニングで困ったとしたら、「上司の人にこういう時にどうすれば良いか聞いてみよう。」と上司とのコミュニケーションを図るという行動をするかもしれませんし、「次の具体的なアクションはこうだ。」と自己解決することができるかもしれません。
このように今の自分自身を受け入れて、次の選択をして行動を起こすというサイクルを踏んでいくだけでも、成長マインドセットを養うことにつながり、どんな種類であれ、能力を高めることにつながります。
ACTについては下記の記事でも取り扱っていますので参考にしてみてください。
まとめ
能力とスキルの違いはパラメータかノウハウかの違いです。能力はスキルよりも基盤となる表現で、スキルを多く身につけることによって能力が高まります。
能力を高めるためには、マインドセットと業界共通の能力が重要です。マインドセットで重要なのは成長マインドセットと呼ばれる物事の考え方・捉え方を養うことで、業界共通の能力とは、ソーシャルスキルなどの社会人としての基盤となるスキルです。
成長マインドセットを養うための思考方法としては、心理学領域で近年注目されているACT(Acceptance& Commitment Therapy)があり、今の自分自身を受け入れて、選択し判断するというサイクルを踏みます。
ACTのサイクルを踏むことによって、成長マインドセットが養われて、どんな能力・スキルでも身につけやすくなります。
本記事を参考にして能力・スキルを高めてみてはいかがでしょうか。
その他にもスキルについて触れている記事がありますので参考にしてみてください。
引用参考文献
1) 「Longman English dictionaries」<https://www.ldoceonline.com>(2019年6月20日アクセス)
2) Kenneth J. Reid& Daniel M. Ferguson(2011). Enhancing the Entrepreneurial Mindset of Freshman Engineers, 2011 Frontiers in Education Conference(FIE). DOI: 10.1109/FIE.2011.6142734(cited 2019-6-20)
3) 井芹まい(2016).大学生の社会的資質・能力に関する近年の研究動向―国内における心理測定尺度に着目して―,早稲田大学大学院教育学研究科紀要,24(1):93-103.
スポーツコーチ同士の学びの場『ダブル・ゴール・コーチングセッション』

NPO法人スポーツコーチング・イニシアチブではこれまで、長年スポーツコーチの学びの場を提供してきました。この中で、スポーツコーチ同士の対話が持つパワーを目の当たりにし、お互いに学び合うことの素晴らしさを経験しています。
答えの無いスポーツコーチの葛藤について、さまざまな対話を重ねながら現場に持ち帰るヒントを得られる場にしたいと考えています。
主なテーマとしては、子ども・選手の『勝利』と『人間的成長』の両立を目指したダブル・ゴール・コーチングをベースとしながら、さまざまな競技の指導者が集まり対話をしたいと考えています。
開催頻度は毎週開催しておりますので、ご興味がある方は下記ボタンから詳しい内容をチェックしてみてください。
ダブル・ゴール・コーチングに関する書籍
NPO法人スポーツコーチング・イニシアチブでは、子ども・選手の『勝利と人間的成長の両立』を目指したダブル・ゴールの実現に向けて日々活動しています。
このダブル・ゴールという考え方は、米NPO法人Positive Coaching Allianceが提唱しており、アメリカのユーススポーツのスタンダードそのものを変革したとされています。
このダブル・ゴールコーチングの書籍は、日本語で出版されている2冊の本があります。
エッセンシャル版書籍『ダブル・ゴール・コーチングの持つパワー』

序文 フィル・ジャクソン
第1章:コーチとして次の世代に引き継ぐもの
第2章:ダブル・ゴール・コーチ®
第3章:熟達達成のためのELMツリーを用いたコーチング
第4章:熟達達成のためのELMツリー実践ツールキット
第5章:スポーツ選手の感情タンク
第6章:感情タンク実践ツールキット
第7章:スポーツマンシップの先にあるもの:試合への敬意
第8章:試合への敬意の実践ツールキット
第9章:ダブル・ゴール・コーチのためのケーススタディ(10選)
第10章:コーチとして次の世代に引き継ぐものを再考する
本格版書籍『ダブル・ゴール・コーチ(東洋館出版社)』

元ラグビー日本代表主将、廣瀬俊朗氏絶賛! 。勝つことを目指しつつ、スポーツを通じて人生の教訓や健やかな人格形成のために必要なことを教えるために、何をどうすればよいのかを解説する。全米で絶賛されたユーススポーツコーチングの教科書、待望の邦訳!
子どもの頃に始めたスポーツ。大好きだったその競技を、親やコーチの厳しい指導に嫌気がさして辞めてしまう子がいる。あまりにも勝利を優先させるコーチの指導は、ときとして子どもにその競技そのものを嫌いにさせてしまうことがある。それはあまりにも悲しい出来事だ。
一方で、コーチの指導法一つで、スポーツだけでなく人生においても大きな糧になる素晴らしい体験もできる。本書はスポーツのみならず、人生の勝者を育てるためにはどうすればいいのかを詳述した本である。
ユーススポーツにおける課題に関する書籍『スポーツの世界から暴力をなくす30の方法』

バレーが嫌いだったけれど、バレーがなければ成長できなかった。だからこそスポーツを本気で変えたい。暴力暴言なしでも絶対強くなれる。「監督が怒ってはいけない大会」代表理事・益子直美)
ーーーーー
数えきれないほど叩かれました。
集合の際に呼ばれて、みんなの目の前で顔を。
血が出てたんですけれど、監督が殴るのは止まらなかった……
(ヒューマン・ライツ・ウォッチのアンケートから)
・殴る、はたく、蹴る、物でたたく
・過剰な食事の強要、水や食事の制限
・罰としての行き過ぎたトレーニング
・罰としての短髪、坊主頭
・上級生からの暴力·暴言
・性虐待
・暴言
暴力は、一種の指導方法として日本のスポーツ界に深く根付いている。
日本の悪しき危険な慣習をなくし、子どもの権利・安全・健康をまもる社会のしくみ・方法を、子どものスポーツ指導に関わる第一線の執筆陣が提案します。


























コメントを残す