9月28日に行われたラグビーワールドカップ2019の日本第2戦、優勝候補の世界ランク2位アイルランドを19対12で見事撃破。
日本中に感動をもたらしてくれましたね!
準備を重ね、勝つべくして勝ったように私の目には映りました。
決してまぐれの勝利ではない。
強い相手に立ち向かう姿をみせてくれて、勇気をもらえたという人も多いのではないでしょうか。
試合後両チームがお互いを称えるために花道を作り合ったシーンに胸を打たれました。
試合が終われば敵も味方もない、まさにノーサイドの精神。チームメイト、対戦相手、レフリーを称え合う姿にジーン、そのシーンを何度も繰り返し観てしまうほどでした。
尊敬の心は素晴らしいというだけではなく、ハイパフォーマンスを生み出します。
この記事では、ノーサイドの精神をスポーツ心理学の観点から解説していきます。
尊敬の心とは、人やスポーツを敬った視点で見る心のレンズである

ここで言う尊敬とは、“人やスポーツを尊いものと認めて敬う心”という意味で述べていきます。
僕ら人間は、意識的にも無意識的にも、現実に起こった事実を自分なりに評価しています。
例えば、目の前にコップ半分の水があったとして、「コップに半分も水が残っている」という捉え方をあれば、「コップに半分しか水が残っていない」という捉え方もできます。
同じ現実でも、捉え方によって、喜びが出ることもあれば、悲しみが出ることもありえます。
つまり、起こった事実が直接的に感情を湧き起こさせているのではなく、現実を見る心のレンズを通して、感情が作り出されているのです。
話を元に戻しますが、スポーツや人を尊いものと認めて敬うということは、そのスポーツや目の前の人をポジティブな心のレンズで見るということです。
ポジティブな心のレンズで物事をみると、ポジティブな感情、ネガティブな感情どちらが多く生まれてくるでしょうか?
当然、ポジティブな感情が生まれやすくなります。
ポジティブ感情がもたらすメリット

では、なぜポジティブな感情が生まれるといいのでしょうか?
ポジティブな感情には、大きく分けて2つのパワーがあります。
それは、①視野を広げ発想を豊かにすること、②脳の機能を高め成長を促すこと、です (拡張-形成理論. Fredrickson, 2001)。
楽しい、嬉しい、できる、希望、興味、感謝、そして尊敬の念…などのポジティブな感情を纏っている時、人は目の前のことに没頭できるようになります。
シンプルに僕らは、ポジティブな感情を感じていたいのです。
この没頭が、特に洞察力、創造力、そして記憶力といった力を引き出してくれます。
楽しかった思い出のことをよく憶えていたり、快適なメンバーで打ち合わせしている時アイディアが溢れてくるなんて経験ありませんか?
まさにそれらがポジティブ感情のチカラです。
このチカラを活用しない手はないですよね。
ポジティブ感情とハイパフォーマンスの関係

スポーツで言えば、ポジティブな感情を纏うことで、クリエイティブなプレーやフローと呼ばれる没頭状態を生み、ハイパフォーマンスに繋がりやすくなります。
また、長期的な視点においても、高い意欲が練習の質を高め、成長を促すことは想像しやすいと思います。
昨今、トップアスリートのインタビューなどで、“楽しむことを最優先にしている”といった発言を聞くことが増えてきました。
大坂なおみ選手、中島翔哉選手、大谷翔平選手などがその最たる例ですが、おそらく感覚的に、どうすればハイパフォーマンスに繋がるのか感覚的に理解されているのでしょうね。
尊敬の心をもつことポジティブな心のレンズとなり、ポジティブな感情を生み出す。
そして、そのポジティブな感情がハイパフォーマンスや成長を促すということなのです。
オリンピックの信条とノーサイドの精神に共通するプロセス志向

少し話は大きくなりますが、ノーサイドの精神は、オリンピック・パラリンピックで正式に制定されているクリード(信念)やモットーに共通する部分があります。
五輪クリード:“The essential thing is not to have conquered but to have fought well.”
五輪モットー:“Faster, Higher, Stronger”
相手を打ち負かすことが大事なのではなく、より早く、より高く、より強くを目指し、全力を出し戦うことに意義があるという意味です。
己のベストを目指すプロセスに重きをおくことを成長マインドセット(その反対は固定マインドセット)と呼びますが、このクリードとモットーは成長マインドセットを育みます。
きれいごとに聞こえるかもしれませんが、このような成長を重要視する心のレンズを持つことが実力発揮や成長を促します。
その理由の一つは先に述べてきた通り、ポジティブな感情を持ちやすいからです。
勝ち負けという自分のコントロールができないことに気を揉むことが減り、自分のやるべきことに意識が向けやすくなるのです。
メンタルトレーニングの大きな目的の一つが、この成長マインドセットを育むことでもあります。
試合以外では敵や味方もなく尊重し合うことが、ラグビーでいうノーサイドの精神。
どちらのチームが勝っているなどという結果主義の心のレンズを取っ払った在り方です。
相手を打ち負かすことが目的ではなく、チームの隔たりを持たずに、切磋琢磨ながら成長しあうことに重きおく。
両チームが花道を作り合うシーンを見て、成長マインドセットを育んでくれる素晴らしい精神であると、つくづく感じました。
まとめ
人やスポーツを尊いものと認めて敬うこと。
これはマナーであると同時に、自分自身の成長やパフォーマンスを促してくれる、自分が生きる世界を変える心のレンズでもあります。
人生の教訓を伝えてくれる素晴らしいスポーツ、ラグビー。
残りのラグビーワールドカップでも、どこが勝つかのみならず、全チームの素晴らしいスポーツマンシップに注目して観戦してみてはいかがでしょうか?
参考文献
1) Amy L. Baltzell (2011). Living in the Sweet Spot. Morgantown, WV: Fitness Information Technology.
2) Fredrickson, B. L. (2001). The role of positive emotions in positive psychology: The broaden-and-build theory of positive emotions. American psychologist, 56(3), 218.
3) Torres, C. R. (2006). Results or participation?: Reconsidering Olympism’s approach to competition. Quest, 58(2), 242-254.
スポーツコーチ同士の学びの場『ダブル・ゴール・コーチングセッション』

NPO法人スポーツコーチング・イニシアチブではこれまで、長年スポーツコーチの学びの場を提供してきました。この中で、スポーツコーチ同士の対話が持つパワーを目の当たりにし、お互いに学び合うことの素晴らしさを経験しています。
答えの無いスポーツコーチの葛藤について、さまざまな対話を重ねながら現場に持ち帰るヒントを得られる場にしたいと考えています。
主なテーマとしては、子ども・選手の『勝利』と『人間的成長』の両立を目指したダブル・ゴール・コーチングをベースとしながら、さまざまな競技の指導者が集まり対話をしたいと考えています。
開催頻度は毎週開催しておりますので、ご興味がある方は下記ボタンから詳しい内容をチェックしてみてください。
ダブル・ゴール・コーチングに関する書籍
NPO法人スポーツコーチング・イニシアチブでは、子ども・選手の『勝利と人間的成長の両立』を目指したダブル・ゴールの実現に向けて日々活動しています。
このダブル・ゴールという考え方は、米NPO法人Positive Coaching Allianceが提唱しており、アメリカのユーススポーツのスタンダードそのものを変革したとされています。
このダブル・ゴールコーチングの書籍は、日本語で出版されている2冊の本があります。
エッセンシャル版書籍『ダブル・ゴール・コーチングの持つパワー』

序文 フィル・ジャクソン
第1章:コーチとして次の世代に引き継ぐもの
第2章:ダブル・ゴール・コーチ®
第3章:熟達達成のためのELMツリーを用いたコーチング
第4章:熟達達成のためのELMツリー実践ツールキット
第5章:スポーツ選手の感情タンク
第6章:感情タンク実践ツールキット
第7章:スポーツマンシップの先にあるもの:試合への敬意
第8章:試合への敬意の実践ツールキット
第9章:ダブル・ゴール・コーチのためのケーススタディ(10選)
第10章:コーチとして次の世代に引き継ぐものを再考する
本格版書籍『ダブル・ゴール・コーチ(東洋館出版社)』

元ラグビー日本代表主将、廣瀬俊朗氏絶賛! 。勝つことを目指しつつ、スポーツを通じて人生の教訓や健やかな人格形成のために必要なことを教えるために、何をどうすればよいのかを解説する。全米で絶賛されたユーススポーツコーチングの教科書、待望の邦訳!
子どもの頃に始めたスポーツ。大好きだったその競技を、親やコーチの厳しい指導に嫌気がさして辞めてしまう子がいる。あまりにも勝利を優先させるコーチの指導は、ときとして子どもにその競技そのものを嫌いにさせてしまうことがある。それはあまりにも悲しい出来事だ。
一方で、コーチの指導法一つで、スポーツだけでなく人生においても大きな糧になる素晴らしい体験もできる。本書はスポーツのみならず、人生の勝者を育てるためにはどうすればいいのかを詳述した本である。
ユーススポーツにおける課題に関する書籍『スポーツの世界から暴力をなくす30の方法』

バレーが嫌いだったけれど、バレーがなければ成長できなかった。だからこそスポーツを本気で変えたい。暴力暴言なしでも絶対強くなれる。「監督が怒ってはいけない大会」代表理事・益子直美)
ーーーーー
数えきれないほど叩かれました。
集合の際に呼ばれて、みんなの目の前で顔を。
血が出てたんですけれど、監督が殴るのは止まらなかった……
(ヒューマン・ライツ・ウォッチのアンケートから)
・殴る、はたく、蹴る、物でたたく
・過剰な食事の強要、水や食事の制限
・罰としての行き過ぎたトレーニング
・罰としての短髪、坊主頭
・上級生からの暴力·暴言
・性虐待
・暴言
暴力は、一種の指導方法として日本のスポーツ界に深く根付いている。
日本の悪しき危険な慣習をなくし、子どもの権利・安全・健康をまもる社会のしくみ・方法を、子どものスポーツ指導に関わる第一線の執筆陣が提案します。

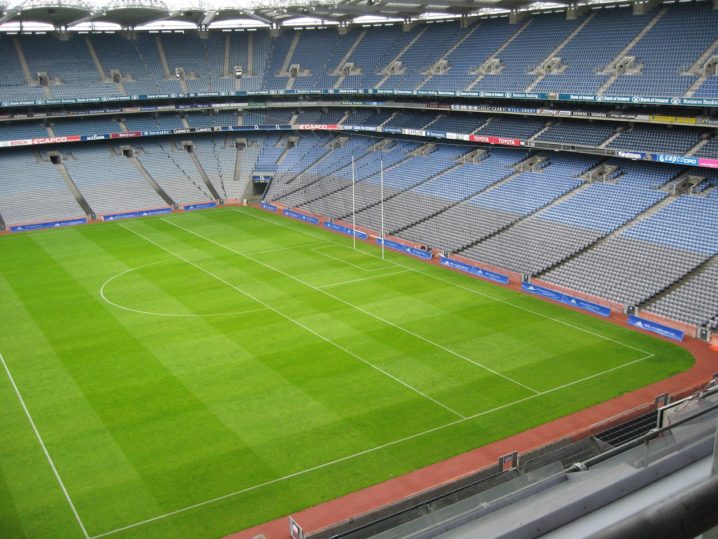





















コメントを残す