この連載では、子どもの地域スポーツにかかわった経験を持つ心理学者が、「ふつうの子ども」とスポーツのかかわりについて考えていきます。 目を輝かせてスポーツを始めたはずの子どもが数年後やめてしまうのはなぜでしょうか? 先日出版した著書「ジュニアスポーツコーチに知っておいてほしいこと」(大橋 恵, 藤後 悦子, 井梅 由美子 共著 / 勁草書房 / 2018年)に基づき、スポーツの入り口である小学生時代を焦点に、プロを目指さないふつうの子どもが、楽しくスポーツを続けていける環境づくりについて提案していけたらと思います。
前回コラムではスポーツ・ハラスメントを紹介しました。
しかし、子どもたちを指導していると、「叱る」必要性が高い場面に遭遇してしまいます。
たとえば、練習にしっかり取り組んでいない、忘れ物をする、教えた通りのプレーができていない、道具を粗末に扱う、移動中に他の乗客に迷惑となるような行動を取るなどです。
スポーツ・ハラスメントを意識しすぎると、このようなときにどのように叱ったらよいのかわからなくなってしまうかもしれません。
今回は叱るときに心にとめておいてほしいこととして、「叱っても怒らない」「誰が責任を持つべき課題か考える」「子どもと対等に」の3点を中心にお話したいと思います。
「叱る」と「怒る」
短所の改善なしに成長させることは難しいので、指導者が選手と対等な立場に立って、相手の気づきを促すために否定的な内容のフィードバックを行うことは構いません。
ただし、「叱る」と「怒る」は別だということです。大辞林(三省堂)によれば、それぞれの一番初めに以下のように書かれています。
叱る:(目下の者に対して)相手のよくない言動をとがめて、強い態度で責める。
怒る:腹を立てる。立腹する。いかる。
「叱る」は相手の良くない言動を指摘することに、「怒る」は自分の感情に、焦点が当たっています。
なんのために「叱る」のか
ここで、考えてみてほしいのです。私たちはどのような目的で子どもたちを「叱る」のでしょうか。
自分の評価を上げるためでも、自分への叱責を避けるためでもありませんよね。技術と人格の両面を含む、子どもの成長のためですよね。
指導者の方の中には、子どもたちやチームの成績が自分の成績のように感じられる方もいらっしゃると思います。
時間とエネルギーと愛情をかけて指導されているがゆえに、選手たちがご自分の一部のように感じられてしまうのでしょう。
しかし、区別して使い分けることが大事です。ここでは、オーストリア出身の精神科医アルフレッド・アドラーが始めたアドラー心理学(岸見,1999)の手法が有効です。
アドラー心理学では、過去の出来事にとらわれるのではなく、過去の出来事の意味づけを重視し、失敗を糧にした改善を目指します。
大人たちは、子どもたちが失敗を受け入れ、改善を考える手伝い(「勇気づけ」と呼ばれます)をすることが奨励されます。
その際、経過(プロセス)を重視し、子どもであっても対等に扱い、「課題の分離」に留意する点に特徴があります。
課題の分離:誰が責任を持つべき課題なのか?
ここでは、叱る時に役に立つ「課題の分離」について説明します。
「課題の分離」とは、目の前で起こっている出来事において誰が困っていて最終的には誰の責任であるかを明らかにすることを指します。
スポーツにおける指導者と子どもの関係においても、自宅での親子の関係においても、誰の責任であるかを明らかにすることは難しいことです。
例えば、ミニバスの試合で指導しているチームが負けるとは思っていなかった相手に負け、地区大会に進めなかったとします。
子どもたちはがっかりして、いらいらしています。あなたも内心がっかりして、つい苛々しながら、「日ごろ真面目に基礎練習をしていないから負けたんだ」などと、くどくど説教をしてしまったとします。
しかし、「敗退」というこの出来事は誰の課題なのでしょうか。
子どもたちの課題
子供たちに責任がある場合は、期待通りに行かず憤りや悔しさを感じていることでしょう。
パスでミスをした、シュートを外した、リバウンドを取られた、走り負けたなどの敗北の原因をそれぞれが考え、対応する必要があります。
この時に指導者はアドバイスすることはできますが、努力すべきなのは子どもたちです。
子どもたち自身が課題を解決できるように、あなたは、温かく見守り声をかけていきましょう。
指導者自身の課題
この出来事は、指導者自身の課題だとも考えることもできます。自分の指導者としての自信が傷ついてしまったからです。
その場合、練習や声掛けを含む準備は適切であったかを見直す必要があるでしょう。たとえば下記のような対策が挙げられます。
- もっとシュート練習をさせる
- 体力が不足しているようだから走り込みをメニューに入れるようにする
- シュートをためらった子がいたから自信をつけさせるような声掛けを多くする
このように、指導者自身の対応策もたくさんあります。
子どもと対等に
否定的なフィードバックを受けるのは誰しもいやなものです。
自己肯定感の育成を重視した最近の子育て本やポジティブ・コーチング・アライアンスの「ダブル・ゴール・コーチング」等では、5つ良い所を指摘してから1つ短所の指摘をするように勧めています。
また、時間を空けると印象が薄れてしまうので、問題があると感じたらできる限り即時にフィードバックすることをお勧めします。
スポーツにおいてもこれらは有効で、特に年少の子どもに対応する時には気をつけた方が良いでしょう。
ここでもう一つ大切なのは、良い所に着目し指摘することはすなわち褒めることだととらえる人が多いと思うのですが、「褒めること」には評価が含まれるということです。
アドラー心理学では、子どもに対しても対等な扱いをすることを奨励します「よくできたね」「頑張ったね」など子どもを主語にした表現では、どうしても上からの評価という面が出てしまいます。
これを「(よくできたことが)うれしい」「(あなたの頑張る姿が)素敵だった」など、自分を主語にした言葉(Iメッセージ)で表現してみましょう。
自分の気持ちを伝え喜びを共有することが、子どもたちにとって「勇気づけ」になるのです。
引用文献
・岸見一郎(1999). アドラー心理学入門 KKベストセラーズ
大橋 恵 プロフィール
東京未来大学教授、早稲田大学非常勤講師。東京大学大学院人文社会系研究科修了、博士(社会心理学)。地域スポーツの保護者・指導者の影響や、日本人の人間理解について研究している。
著者たちのHP https://togotokyo101.wixsite.com/mysite
スポーツコーチ同士の学びの場『ダブル・ゴール・コーチングセッション』

NPO法人スポーツコーチング・イニシアチブではこれまで、長年スポーツコーチの学びの場を提供してきました。この中で、スポーツコーチ同士の対話が持つパワーを目の当たりにし、お互いに学び合うことの素晴らしさを経験しています。
答えの無いスポーツコーチの葛藤について、さまざまな対話を重ねながら現場に持ち帰るヒントを得られる場にしたいと考えています。
主なテーマとしては、子ども・選手の『勝利』と『人間的成長』の両立を目指したダブル・ゴール・コーチングをベースとしながら、さまざまな競技の指導者が集まり対話をしたいと考えています。
開催頻度は毎週開催しておりますので、ご興味がある方は下記ボタンから詳しい内容をチェックしてみてください。
ダブル・ゴール・コーチングに関する書籍
NPO法人スポーツコーチング・イニシアチブでは、子ども・選手の『勝利と人間的成長の両立』を目指したダブル・ゴールの実現に向けて日々活動しています。
このダブル・ゴールという考え方は、米NPO法人Positive Coaching Allianceが提唱しており、アメリカのユーススポーツのスタンダードそのものを変革したとされています。
このダブル・ゴールコーチングの書籍は、日本語で出版されている2冊の本があります。
エッセンシャル版書籍『ダブル・ゴール・コーチングの持つパワー』

序文 フィル・ジャクソン
第1章:コーチとして次の世代に引き継ぐもの
第2章:ダブル・ゴール・コーチ®
第3章:熟達達成のためのELMツリーを用いたコーチング
第4章:熟達達成のためのELMツリー実践ツールキット
第5章:スポーツ選手の感情タンク
第6章:感情タンク実践ツールキット
第7章:スポーツマンシップの先にあるもの:試合への敬意
第8章:試合への敬意の実践ツールキット
第9章:ダブル・ゴール・コーチのためのケーススタディ(10選)
第10章:コーチとして次の世代に引き継ぐものを再考する
本格版書籍『ダブル・ゴール・コーチ(東洋館出版社)』

元ラグビー日本代表主将、廣瀬俊朗氏絶賛! 。勝つことを目指しつつ、スポーツを通じて人生の教訓や健やかな人格形成のために必要なことを教えるために、何をどうすればよいのかを解説する。全米で絶賛されたユーススポーツコーチングの教科書、待望の邦訳!
子どもの頃に始めたスポーツ。大好きだったその競技を、親やコーチの厳しい指導に嫌気がさして辞めてしまう子がいる。あまりにも勝利を優先させるコーチの指導は、ときとして子どもにその競技そのものを嫌いにさせてしまうことがある。それはあまりにも悲しい出来事だ。
一方で、コーチの指導法一つで、スポーツだけでなく人生においても大きな糧になる素晴らしい体験もできる。本書はスポーツのみならず、人生の勝者を育てるためにはどうすればいいのかを詳述した本である。
ユーススポーツにおける課題に関する書籍『スポーツの世界から暴力をなくす30の方法』

バレーが嫌いだったけれど、バレーがなければ成長できなかった。だからこそスポーツを本気で変えたい。暴力暴言なしでも絶対強くなれる。「監督が怒ってはいけない大会」代表理事・益子直美)
ーーーーー
数えきれないほど叩かれました。
集合の際に呼ばれて、みんなの目の前で顔を。
血が出てたんですけれど、監督が殴るのは止まらなかった……
(ヒューマン・ライツ・ウォッチのアンケートから)
・殴る、はたく、蹴る、物でたたく
・過剰な食事の強要、水や食事の制限
・罰としての行き過ぎたトレーニング
・罰としての短髪、坊主頭
・上級生からの暴力·暴言
・性虐待
・暴言
暴力は、一種の指導方法として日本のスポーツ界に深く根付いている。
日本の悪しき危険な慣習をなくし、子どもの権利・安全・健康をまもる社会のしくみ・方法を、子どものスポーツ指導に関わる第一線の執筆陣が提案します。

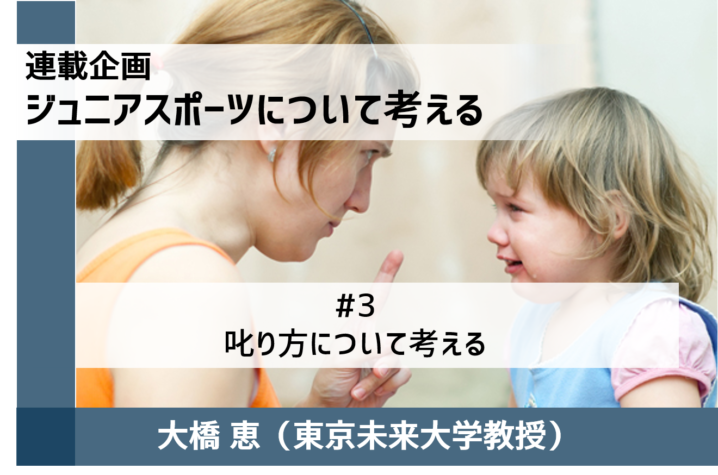



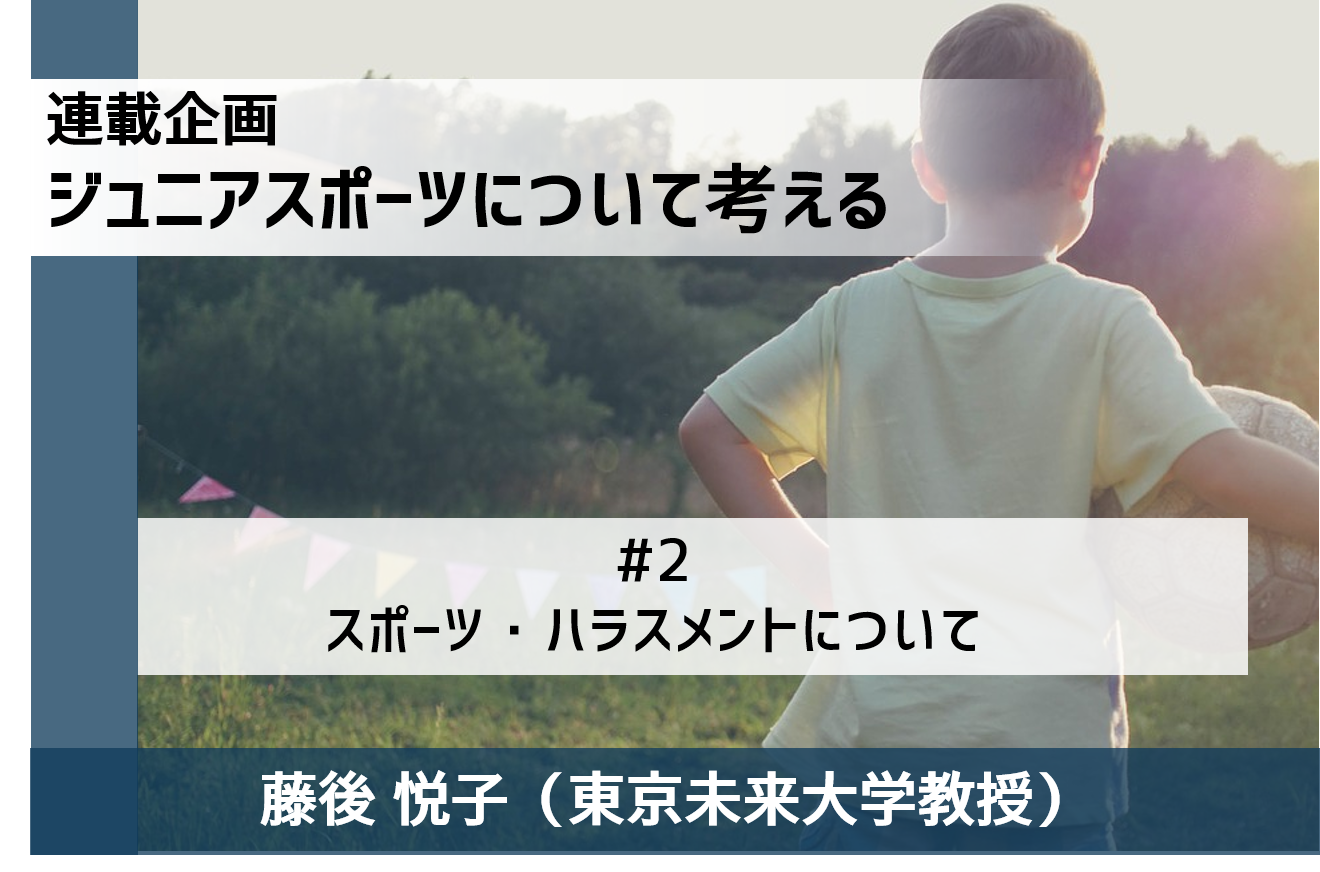






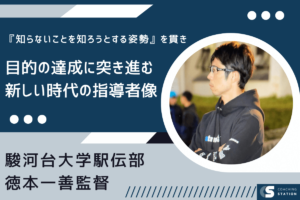














コメントを残す