新連載「Spiral Eye」
この連載では、現役の体育教師かつコーチの筆者が、スポーツを様々な観点から分析していきます。複雑に絡み合いながらできているスポーツ界の螺旋構造をより良い方向に導いていくための方法を探ります。
初回のテーマは、「オリンピックメダリストの育ち方」。
夏季五輪のメダル種目を分析し、その競技でメダリストが育つ要因を挙げていきます。世界と互角に戦える日本のアスリートは、どんな環境で育つのか、スポーツの歴史とともにお伝えします。
前編では、オリンピックメダリストには部活育ちが少ないことから、ジュニア期の育成の重要性に触れました。
後編では、「競技種目」という観点から考察します。
————–
次の表を見てほしい。
以下は日本の夏季五輪初参加の1920年から東京五輪前の1960年までの8大会と1964年の東京五輪から1996年までの8大会、そして2000年から2016年の五輪の5大会で日本が獲得したメダル数とそれぞれの種目である。

メダリストを育てる民間スポーツクラブ
この表を見ると、近年日本は大会ごとに獲得するメダル数を徐々に増やしているが、メダルを獲得している種目の多くは、必ずしもスポーツ人口の多い種目ではないことがわかる。
浅く広く普及した種目というよりも、一つの種目に深く集中することでメダルにつなげている。これには、それぞれの種目を教える民間のスポーツクラブの存在が大きいといえよう。
1964年の東京五輪以前、日本で月謝を払って教えてもらう民間のスポーツクラブは柔道、剣道等日本伝統の武道が中心で、その他はほんの限られた種目のみだった。
当時はまだ営利が問われる民間のクラブは採算が合わなかったのであろう。スポーツ指導ではお金が稼げない時代だったのである。
そのため、1964年の東京五輪までの選手育成の流れは、小中学校の体育や部活動でスポーツを習い、高校から大学にかけて学校の先生やコーチに恵まれて練習を積む。
さらに大学で猛練習をして、実業団や自衛隊体育学校等で練習を続け、五輪のメダルにつなげたという流れで勝負するほかなかった。
1964年の東京五輪後、スポーツ振興のムードが盛り上がる中、日本の水泳を再興したいという熱意のあるコーチが、実業家を巻き込み、スイミングクラブが作られた。
子どもたちが溺れないように泳ぎを覚えさせておきたいと考える多くの親が子どもをスイミングクラブに入れるようになり、スイミングクラブは各地に普及していった。
習い事の幅を広げたスイミングクラブ
スイミングクラブの普及は、日本の子どもたちの習い事の幅をスポーツを含むものへと広げた。ピアノ、塾の先生に月謝を払うのは当たり前でも、学校の部活動でスポーツを習うことに、お金を払う必要はないと親たちは考えていた。
しかし、スイミングクラブの出現により、学校で習えるスポーツであっても、水泳は月謝を払って覚えさせる価値のあるスポーツであると考えられるようになった。
スイミングクラブのコーチには子どもたちへの水泳の普及指導をする一方で、トップ選手に育て上げるという広告的な役割がある。
一流選手を育てることがスイミングクラブのコーチの給与アップ、待遇の改善、ひいてはクラブの繁栄につながるので、コーチも真剣になって選手の指導育成方法の研究をするようになった。
一方、学校での部活動は一部の強豪校を除いて、体育科以外の教員が指導する旧態依然の体制のままだ。
指導者はスポーツ未経験の教員も多く、精神論は伝えられても育成につながる正しい基礎技術を教えられる教員は少ないままである。
はた目には学校で優秀な選手が育てられているように見える強豪校でも、ジュニア時代に民間のクラブで指導され、その高い技術を武器に高校に進学し、活躍する選手も多い。
体操や水泳の場合は自校のユニフォームは着ていても進学後の練習は民間クラブのコーチに教えられている場合がほとんどで、この体制は大学にも受け継がれている。
強豪チームの内情は民間クラブ育ちの選手をスカウトして集めた集合体である場合が多くなっているのである。
子どもたちに多様なスポーツの体験を
近年、世界で多くの新しいスポーツが生まれ競技人口を増やしている。
その影響で、五輪種目もさらに多様化してきた。2020年に導入を検討された、ウエイクボードやスカッシュも日本人にはなじみが薄くても、他の国で人気であればいつかは五輪に導入されることであろう。
また、コンピューターゲームをスポーツと見なそうという流れもあり、「e-Sports(エレクトロニック・スポーツ)」も五輪種目になる時代も迫ってきている。
私はメダル獲得至上主義者ではないが、日本のスポーツが五輪でのメダル獲得を大きな目標と掲げるのであれば、多様化するニュースポーツを柔軟に取り入れ、若者たちに幅広く普及させていく必要がある。
競技人口の少ない種目で少数精鋭の選手を育てていくためには、多くの子どもたちに多様なスポーツ種目を体験させることが重要である。
そして、そのような体験の中で、子どもたちは自己の素質を発見し、その種目の優秀なコーチにジュニア時代から指導してもらうことが、五輪でのメダル獲得につながっていくことだろう。

コラムニスト プロフィール
田邊潤 (たなべ・じゅん)
早稲田大学本庄高等学院教諭。同校陸上競技部を31年間指導。関東大会、インターハイの常連で埼玉県の強豪校として知られる。1957年生まれ。早稲田大学教育学部卒、筑波大学体育研究科大学院修士課程修了。専門は陸上競技で走り高跳び国体8位。早稲田大学研究員としてアメリカや中国に滞在し、ジュニアの指導法や健康法を研究。早稲田大学非常勤講師。日本陸上競技学会、日本スプリント学会に所属。
スポーツコーチ同士の学びの場『ダブル・ゴール・コーチングセッション』

NPO法人スポーツコーチング・イニシアチブではこれまで、長年スポーツコーチの学びの場を提供してきました。この中で、スポーツコーチ同士の対話が持つパワーを目の当たりにし、お互いに学び合うことの素晴らしさを経験しています。
答えの無いスポーツコーチの葛藤について、さまざまな対話を重ねながら現場に持ち帰るヒントを得られる場にしたいと考えています。
主なテーマとしては、子ども・選手の『勝利』と『人間的成長』の両立を目指したダブル・ゴール・コーチングをベースとしながら、さまざまな競技の指導者が集まり対話をしたいと考えています。
開催頻度は毎週開催しておりますので、ご興味がある方は下記ボタンから詳しい内容をチェックしてみてください。
ダブル・ゴール・コーチングに関する書籍
NPO法人スポーツコーチング・イニシアチブでは、子ども・選手の『勝利と人間的成長の両立』を目指したダブル・ゴールの実現に向けて日々活動しています。
このダブル・ゴールという考え方は、米NPO法人Positive Coaching Allianceが提唱しており、アメリカのユーススポーツのスタンダードそのものを変革したとされています。
このダブル・ゴールコーチングの書籍は、日本語で出版されている2冊の本があります。
エッセンシャル版書籍『ダブル・ゴール・コーチングの持つパワー』

序文 フィル・ジャクソン
第1章:コーチとして次の世代に引き継ぐもの
第2章:ダブル・ゴール・コーチ®
第3章:熟達達成のためのELMツリーを用いたコーチング
第4章:熟達達成のためのELMツリー実践ツールキット
第5章:スポーツ選手の感情タンク
第6章:感情タンク実践ツールキット
第7章:スポーツマンシップの先にあるもの:試合への敬意
第8章:試合への敬意の実践ツールキット
第9章:ダブル・ゴール・コーチのためのケーススタディ(10選)
第10章:コーチとして次の世代に引き継ぐものを再考する
本格版書籍『ダブル・ゴール・コーチ(東洋館出版社)』

元ラグビー日本代表主将、廣瀬俊朗氏絶賛! 。勝つことを目指しつつ、スポーツを通じて人生の教訓や健やかな人格形成のために必要なことを教えるために、何をどうすればよいのかを解説する。全米で絶賛されたユーススポーツコーチングの教科書、待望の邦訳!
子どもの頃に始めたスポーツ。大好きだったその競技を、親やコーチの厳しい指導に嫌気がさして辞めてしまう子がいる。あまりにも勝利を優先させるコーチの指導は、ときとして子どもにその競技そのものを嫌いにさせてしまうことがある。それはあまりにも悲しい出来事だ。
一方で、コーチの指導法一つで、スポーツだけでなく人生においても大きな糧になる素晴らしい体験もできる。本書はスポーツのみならず、人生の勝者を育てるためにはどうすればいいのかを詳述した本である。
ユーススポーツにおける課題に関する書籍『スポーツの世界から暴力をなくす30の方法』

バレーが嫌いだったけれど、バレーがなければ成長できなかった。だからこそスポーツを本気で変えたい。暴力暴言なしでも絶対強くなれる。「監督が怒ってはいけない大会」代表理事・益子直美)
ーーーーー
数えきれないほど叩かれました。
集合の際に呼ばれて、みんなの目の前で顔を。
血が出てたんですけれど、監督が殴るのは止まらなかった……
(ヒューマン・ライツ・ウォッチのアンケートから)
・殴る、はたく、蹴る、物でたたく
・過剰な食事の強要、水や食事の制限
・罰としての行き過ぎたトレーニング
・罰としての短髪、坊主頭
・上級生からの暴力·暴言
・性虐待
・暴言
暴力は、一種の指導方法として日本のスポーツ界に深く根付いている。
日本の悪しき危険な慣習をなくし、子どもの権利・安全・健康をまもる社会のしくみ・方法を、子どものスポーツ指導に関わる第一線の執筆陣が提案します。

-2-718x507.png)

.png)
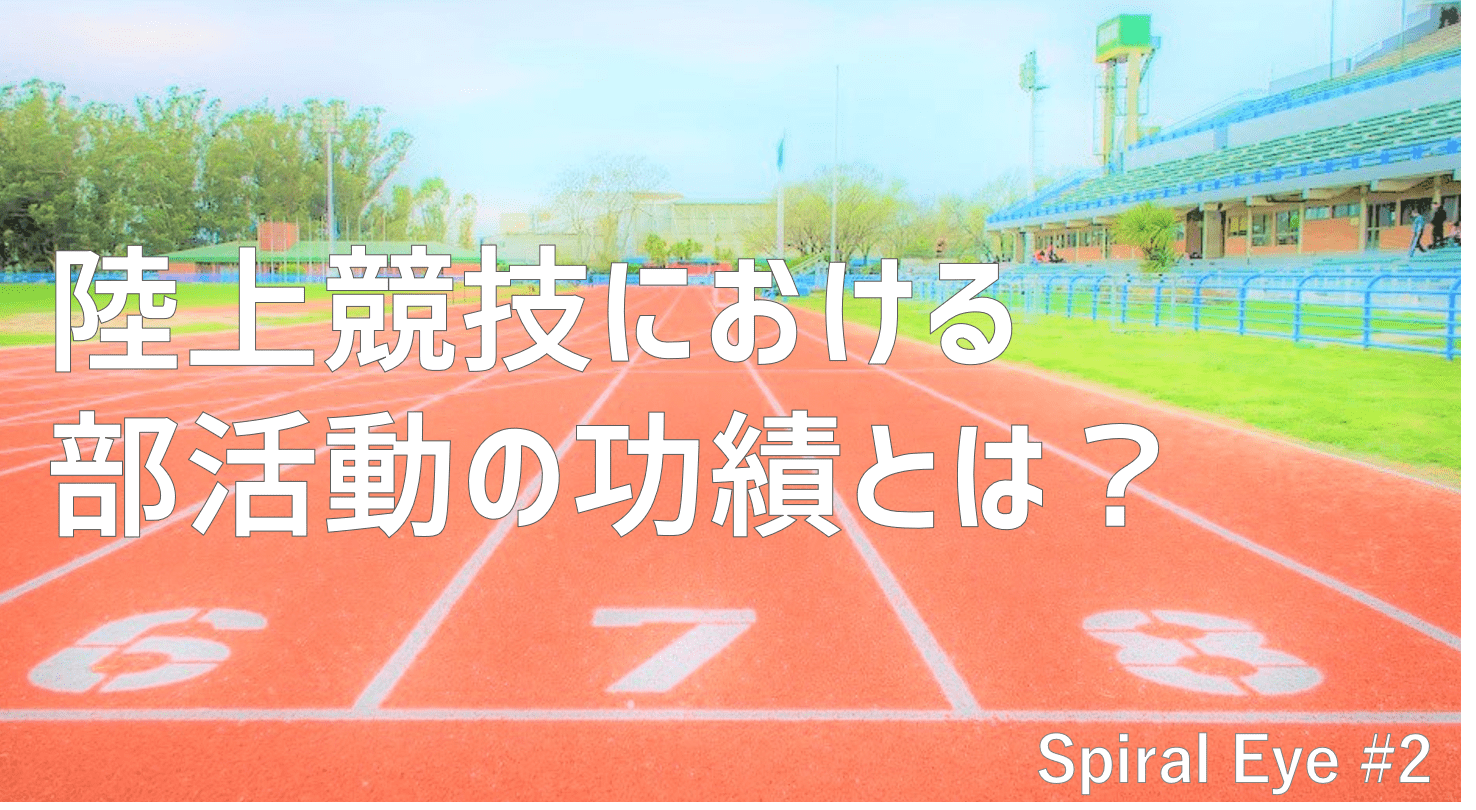






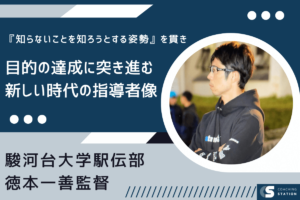














コメントを残す