3月3日に開催されたスポーツコーチングJapanカンファレンス。
最先端の知見を持った方々が登壇する中、日本体育大学教授で「アスリートセンタード・コーチング」を提唱する伊藤雅充氏が登壇されました。
従来のスポーツコーチングの在り方に一石を投じる「アスリートセンタード・コーチング」のエッセンスとは、どのようなものなのでしょうか?
選手の欲求を満たすことが、パフォーマンスを上げ人間性を育てる。
人間のモチベーションに関わる理論の中で、自己決定理論というものがあります。自己決定理論では、人間の欲求として3つを定義しています。
一つ目は「有能感」。これは純粋に「成功したい」という欲求です。次が「自律感」。これは、自分の思った通りにやりたい、自分で決めて自分で動きたい、という欲求です。これがうまくいったときに喜びを感じることができます。
3つ目は「関係性」。仲間の中に入りたい、仲間と良い関係を築きたいという欲求です。この3つの欲求が全て満たされると、モチベーションが上がり、パフォーマンスも上がります。
さらに、この3つの欲求は互いに影響を及ぼしあっています。
チームスポーツの中で、仲間になかなか溶け込めず「関係性」の欲求が満たされないと、パフォーマンスは落ちる。そうすると今度は「有能感」を感じられなくなりますよね。
この3つの欲求を満たすことができれば、スポーツを通して包括的な人間的成長ができるのではないでしょうか。
そして、私たちが「アスリートセンタード・コーチング」、つまり選手を中心に置いて指導することを唱えてる理由も、そもそも選手が自分の欲求が満たされないと、パフォーマンスは上がらないだろうと考えているからです。
選手が楽しめていなければ、成長の天井は見えているようなものです。選手がワクワクすれば、もっと高い領域に行けるのではないかと考えています。コーチは、アスリートの主体的な学びに対する支援をすることが仕事なのです。
「教える」ことにとらわれず、選手に「意思決定」の機会を。

日本人は1つ1つのテクニックは上手いんだけれども、実際の試合になるとそれがうまく出せないとよく言われてます。
僕はバレーボールなんですが、形はすごくきれいなんですよ。オーバーハンドパス、アンダーハンドパス…世界「形」選手権があったら、世界一になれますよ(笑)
しかし、ゲームになるとそう簡単にはきれいな形でプレーすることはできない。これを解決するために私は「ゲームを中心とした練習をしよう」といろんなところで言っています。
ドリル中心ではなく、アスリートセンタードに選手がワクワクするようなゲームを中心に練習しましょうと。
それで、コーチの方々に聞くと、「ゲーム中心でやっています」と多くの方がお答えされるんですが、実際はドリル中心になっていることが多い(笑)
つまり、コーチセンタードで教え込むようなコーチングをやっている。私たちが大事にしているのは、ゲームライクなシチュエーションで選手自身が「意思決定」をすることです。
間違ってもいいから選手が試すことが重要です。コーチたちが「教えなければならない」ということにとらわれていると、ゲーム中心の練習はうまくいかないことが多いんです。
そもそも、コーチたちが現役でプレーしていた頃の「正解」が、今と同じとは限りません。今の子どもたちが10年後に求められているスキルも今とはきっと変わっていきますよね。
僕たちも、コーチング学をやればやるほど「わからないなぁ」と感じています。でも「わからない」ことを前提に、今より良くなるために新しいことに挑戦していくことが重要です。
「何が正しいか」を議論することはあまり意味がありません。僕は、10年後に体罰が正しいとされる時代が来ることを否定はしません。
もちろん、僕自身はしたことがありませんし、正しいとされるとは思いませんが…。
でもその可能性を否定しちゃいけないと思うんです。それより、僕たちがその時々のベストを考えていくことが重要なんです。
合理的な練習ではなく「Play Practice」
イギリスで行われた、ユース年代のサッカー選手を対処とした研究のデータをお見せしたいと思います。
14歳の時にプレミアリーグのユースチームに選ばれた選手が、小学生の時にどのような練習をどれくらい行ったのかを示したグラフです。ユースチームに選ばれた選手と選ばれなかった選手を比較しています。
それを見ると、試合の時間はあまり変わらないのですが、ユースチームに選ばれた選手のほうが練習量が多かったのです。しかし、これからが面白い。
この研究では追跡調査をおこなっていて、ユースの選手でトップチームに昇格した選手とできなかった選手を比較しています。
すると、サッカーの活動の中でうまく遊んでいた選手は昇格しているんですが、練習ばかりをたくさんやっている、大人の言うことを聞いて練習をいっぱいやっていた選手は結構昇格できないケースが多かったのです。
どうですか?これはかなりショッキングですよね。大人たちが良かれと思って教え込んでいることは、子どもたちのクリエイティビティを奪っているかもしれない。
大人が考える合理的な練習だけでは、子どもたちの将来性を奪ってしまうかもしれないのです。クリスチアーノ・ロナウドは子どもの時にコーチがいなかったそうです。
子どもたちに「意思決定」をさせ、かつワクワクできるゲーム中心の練習によって、子どもたちの発想力をもっと豊かにしていくべきではないかと思います。
僕たちが今すごく興味を持っているのは、子どもたちがワクワクするような練習レニューを作ることです。
「Play Practice」、遊びを練習にしちゃえと。ワクワクするから練習しちゃう。発見だってしちゃう。こういう状態に選手がなるようなメニューを作れないか、研究しています。
「コーチが変われば選手は変わる」
私の研究室に、ある柔道のコーチがいます。
そのコーチは現役時代に国際大会で優勝もしている女性の方なのですが、僕たちが彼女と選手との会話を録音して書き起こしをすると、選手は「はい!」としか言っていなかったんですね。
つまり、彼女は教えすぎていたのです。それを受けて研究室の中で相談して、彼女は「GROWモデル」を使うことにしました。
「Goal」「Reality」「Option」「Will」の順番で質問していく、というものです。
「何をやろうとしたの?」「実際どうだった?」「他にやり方ある?」「じゃあそれをやってみよう」というような類の質問を投げかけることで、選手自身の考える力を育てていくことを目指しました。
結果、彼女は私にこう言ってきました。「先生、考えていないのは選手ではなく私でした」と(笑)。
このことに彼女は自分で気づいたんです。そこで自分自身が変わる必要があると気づいたのです。
これは僕たちが提唱している「アスリートセンタード・コーチング」が目指している形です。選手を変えるのではなくコーチ自身が変わる。そして選手も変わる。
「相手は別人」という前提に立って、自分しか自分の事は変えられない、コーチが選手を変えようとしても変わらないと考える。
そして、自分のコントロールできること、つまり自分の行動に意識を集中する。そうすることで選手に対してイライラすることもなくなり、コーチ自身の心の健康のためにもなる。
選手にとってコーチは環境の一部でしかありません。そのコーチが変われば、変化した環境に適応しようとしておのずと選手も変わっていきます。
そもそも世の中は動的で複雑で絶対解がありません。今日うまくいっても明日はそうはいかないかもしれない。
という中で、僕たちは文脈を読み意思決定をし行動し省察するというサイクルを何回も何回もやっていくしかないんです。
つまり、現状維持ではなくより良く「変化」していく能力を身につけていくことが非常に重要だと考えています。

伊藤 雅充
日本体育大学体育学部体育学科教授
国際コーチングエクセレンス評議会科学委員会委員
アジアコーチング科学協会副会長
スポーツコーチ同士の学びの場『ダブル・ゴール・コーチングセッション』

NPO法人スポーツコーチング・イニシアチブではこれまで、長年スポーツコーチの学びの場を提供してきました。この中で、スポーツコーチ同士の対話が持つパワーを目の当たりにし、お互いに学び合うことの素晴らしさを経験しています。
答えの無いスポーツコーチの葛藤について、さまざまな対話を重ねながら現場に持ち帰るヒントを得られる場にしたいと考えています。
主なテーマとしては、子ども・選手の『勝利』と『人間的成長』の両立を目指したダブル・ゴール・コーチングをベースとしながら、さまざまな競技の指導者が集まり対話をしたいと考えています。
開催頻度は毎週開催しておりますので、ご興味がある方は下記ボタンから詳しい内容をチェックしてみてください。
ダブル・ゴール・コーチングに関する書籍
NPO法人スポーツコーチング・イニシアチブでは、子ども・選手の『勝利と人間的成長の両立』を目指したダブル・ゴールの実現に向けて日々活動しています。
このダブル・ゴールという考え方は、米NPO法人Positive Coaching Allianceが提唱しており、アメリカのユーススポーツのスタンダードそのものを変革したとされています。
このダブル・ゴールコーチングの書籍は、日本語で出版されている2冊の本があります。
エッセンシャル版書籍『ダブル・ゴール・コーチングの持つパワー』

序文 フィル・ジャクソン
第1章:コーチとして次の世代に引き継ぐもの
第2章:ダブル・ゴール・コーチ®
第3章:熟達達成のためのELMツリーを用いたコーチング
第4章:熟達達成のためのELMツリー実践ツールキット
第5章:スポーツ選手の感情タンク
第6章:感情タンク実践ツールキット
第7章:スポーツマンシップの先にあるもの:試合への敬意
第8章:試合への敬意の実践ツールキット
第9章:ダブル・ゴール・コーチのためのケーススタディ(10選)
第10章:コーチとして次の世代に引き継ぐものを再考する
本格版書籍『ダブル・ゴール・コーチ(東洋館出版社)』

元ラグビー日本代表主将、廣瀬俊朗氏絶賛! 。勝つことを目指しつつ、スポーツを通じて人生の教訓や健やかな人格形成のために必要なことを教えるために、何をどうすればよいのかを解説する。全米で絶賛されたユーススポーツコーチングの教科書、待望の邦訳!
子どもの頃に始めたスポーツ。大好きだったその競技を、親やコーチの厳しい指導に嫌気がさして辞めてしまう子がいる。あまりにも勝利を優先させるコーチの指導は、ときとして子どもにその競技そのものを嫌いにさせてしまうことがある。それはあまりにも悲しい出来事だ。
一方で、コーチの指導法一つで、スポーツだけでなく人生においても大きな糧になる素晴らしい体験もできる。本書はスポーツのみならず、人生の勝者を育てるためにはどうすればいいのかを詳述した本である。
ユーススポーツにおける課題に関する書籍『スポーツの世界から暴力をなくす30の方法』

バレーが嫌いだったけれど、バレーがなければ成長できなかった。だからこそスポーツを本気で変えたい。暴力暴言なしでも絶対強くなれる。「監督が怒ってはいけない大会」代表理事・益子直美)
ーーーーー
数えきれないほど叩かれました。
集合の際に呼ばれて、みんなの目の前で顔を。
血が出てたんですけれど、監督が殴るのは止まらなかった……
(ヒューマン・ライツ・ウォッチのアンケートから)
・殴る、はたく、蹴る、物でたたく
・過剰な食事の強要、水や食事の制限
・罰としての行き過ぎたトレーニング
・罰としての短髪、坊主頭
・上級生からの暴力·暴言
・性虐待
・暴言
暴力は、一種の指導方法として日本のスポーツ界に深く根付いている。
日本の悪しき危険な慣習をなくし、子どもの権利・安全・健康をまもる社会のしくみ・方法を、子どものスポーツ指導に関わる第一線の執筆陣が提案します。












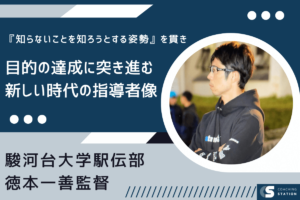



[…] 新時代に求められる「アスリートセンタード・コーチング」(日本体育大学教授 伊藤雅充氏)3月3日に開催されたスポーツコーチングJapanカンファレンス。 最先端の知見を持った方々が […]
アスリートセンタード・コーチングは、〜と言われている、と調べると目にしますが、正確に定義している団体は日本や世界にあるのでしょうか?
”正確に定義”といわれると、具体的な論文を挙げることができませんが、もともとコーチング哲学に関する研究から発展した考え方がアスリートセンタードコーチングです。アスリートセンタードコーチングはアメリカのUSOPCやデンマークのオリンピック委員会なども使用している用語ですので、今後のグローバルスタンダードになるんじゃないかなぁと思います!!
応えになっているかどうかわかりませんが;;