3月3日に開催されたスポーツコーチングJapanカンファレンス2018。
ここでは、花まる学習会代表の高濱正伸さんのセッションをレポートします。
教育のプロから見たスポーツとは、どのようなものなのか?
「教育としてのスポーツ」の持つポテンシャルは何なのか、それを最大限に発揮するためにコーチができることは何なのでしょうか…?
スポーツは地頭を鍛える
今日皆さんにお伝えしたいのは、「スポーツは地頭を鍛える」。これに尽きます。
スポーツを通して、友情が育まれ、忍耐力が伸びる…これは間違いありません。ですが、コーチの皆さんには、スポーツをやっていれば頭の良さは全部鍛えられる!ということに気づいて欲しいんです。
頭の良さというのは、「見える力」と「詰める力」で決まります。
「見える力」というのは、見えないものを見る力です。
「本質」という見えないものが見える、「アイデア」というという見えないものが見える、「相手の言いたいこと」という見えないものが見える。「問題点」という見えないものが見える。
これが見えるかどうかで差がつくんです。数学で言うと、補助線が見えるかどうか…みたいなことですね。
頭の良さその2は「詰める力」です。皆さんが一番よく知っているのは論理力ですね。論理というものは、「必要条件」と「場合分け」という2つのフローチャートを繰り返しているだけなんです。
つまり、答えに向かって条件を狭めて、狭めきれなかった部分を場合分けして答えを出していく。
「偶数かつ70代」というところまで狭めて、そこから2通りの場合があるなら両方やる…というように。こうやって「詰める」ことなんです。良質な入試問題は、この「必要条件」が浮かぶか浮かばないかで差がつくように作られているんです。
これはスポーツと同じです。試合中の一瞬のひらめきと、地道に努力していくこと。前者が「必要条件」で、後者が「場合分け」です。これは数学に顕著に表れます。
「詰める力」がどうやって伸びるか…というと、これはもう「詰めきった」経験をどれだけしてるかです。真剣に詰める経験をしているかどうか。
そして、これこそまさにスポーツで経験できることです。もうすぐ大会で、ゴールに近づいていって、試合寸前の脳の集中した感じが、詰める力を一番伸ばします。
勉強だと、人間どこかでやっぱりやりたくない気持ちがある。だからそこそこしか伸びません。スポーツだから、楽しくて集中して、没頭するから圧倒的に伸びるんです。
それでも、なんでスポーツバカと言われてしまうのか…それは言語の訓練をしていないからです。
だから、スポーツをやりながら日誌を書くことはとても重要で、適当に書かせてはいけない。ひとつの経験から感じたこと、考えたことをしっかりだめ書かせないとダメです。
スポーツは発見と感動に満ちているはずです。それなのに言語化していないんですよね。「すごかったね!」「嬉しかったね!」という言葉だけで終わってしまうことが多いです。
そこをしっかりと言語化していくことで、世界が豊かになるし、大人になってからいろんな物語を語れるようになります。

子どもから何かを「キャッチ」する
現在、花まる学習会は200人くらいの正社員がいます。その中で30人くらいは、僕のように講演をバンバンやったり、本を出していたりしています。それは、言語訓練をしっかりさせているからです。
どのように訓練しているかというと、一回の授業で絶対に子どもたちから何らかの「教育的意味」を拾ってこないと社員としてアウトにしています。
「今日はこれをやりました」という「作業」を1ミリもやらせません。でも、そうやって「キャッチ」する癖をつけると必ずできるようになります。ストーリーだらけになります。
日報も、「今日はみんな輝いていましたね」みたいな、ありきたりで心が込もってない文章は書かせません。お母さんを笑顔にすれば、子どもは伸びるんです。そのために、お母さんを喜ばせるような文章を書かせなければいけない。
それを月に一回全社員にやらせる。そうしたら僕レベルの講演は誰でもできるようになります。
スポーツは「好き」になれる。これがチャンス。
できない子たちの壁は、意識の壁です。一度「得意だ!」と感じられるとずっと好きでいられる。ですが、どこかでやらされ感を感じてしまうと、ある程度できるし結果も出るけど、やっぱりやらされている感が拭えない。
そして自分ができなくなると、「嫌い」とか「苦手」という言葉に逃げてしまう。それは「甘え」だと私ははっきり言い切ります。
「嫌い」とか「苦手」は思い込みです。だから子どもに「嫌い」とか「苦手」と言わせないことがすごく重要です。
でも、本当の犯人は大人だったりするんです。大人が「苦手だよね」と言ってしまうんです。すると子どもは洗脳されて「苦手なんだ」と思ってしまう。そして「嫌い」とか「苦手」という洗脳はその子を一生縛ってしまいます。
大人になっても「俺小さいころ図形苦手だったんだよねー」って言いますよ。「苦手」「嫌い」という言葉で、どれだけの大人が人生を台無しにしているか。
そのような意味では、何でも「楽しい!」と言わせられるスポーツはものすごいチャンスなんだと思います。

高濱 正伸
「メシが食える大人に育てる」という理念のもと、「作文」「読書」「思考力」「野外体験」を主軸にすえた学習塾「花まる学習会」を設立。1995年には、小学校4年生から中学3年生を対象とした進学塾「スクールFC」を設立。チラシなし、口コミだけで、母親たちが場所探しから会員集めまでしてくれる形で広がり、当初20名だった会員数は、23年目で20000人を超す。また、同会が主催する野外体験企画であるサマースクールや雪国スクールは大変好評で、延べ50000人を引率した実績がある。
各地で精力的に行っている、保護者などを対象にした講演会の参加者は年間30000人を超え、毎回キャンセル待ちが出るほど盛況。なかには“追っかけママ”もいるほどの人気ぶり。
障がい児の学習指導や青年期の引きこもりなどの相談も一貫して受け続け、現在は独立した専門のNPO法人「子育て応援隊むぎぐみ」として運営している。
スポーツコーチ同士の学びの場『ダブル・ゴール・コーチングセッション』

NPO法人スポーツコーチング・イニシアチブではこれまで、長年スポーツコーチの学びの場を提供してきました。この中で、スポーツコーチ同士の対話が持つパワーを目の当たりにし、お互いに学び合うことの素晴らしさを経験しています。
答えの無いスポーツコーチの葛藤について、さまざまな対話を重ねながら現場に持ち帰るヒントを得られる場にしたいと考えています。
主なテーマとしては、子ども・選手の『勝利』と『人間的成長』の両立を目指したダブル・ゴール・コーチングをベースとしながら、さまざまな競技の指導者が集まり対話をしたいと考えています。
開催頻度は毎週開催しておりますので、ご興味がある方は下記ボタンから詳しい内容をチェックしてみてください。
ダブル・ゴール・コーチングに関する書籍
NPO法人スポーツコーチング・イニシアチブでは、子ども・選手の『勝利と人間的成長の両立』を目指したダブル・ゴールの実現に向けて日々活動しています。
このダブル・ゴールという考え方は、米NPO法人Positive Coaching Allianceが提唱しており、アメリカのユーススポーツのスタンダードそのものを変革したとされています。
このダブル・ゴールコーチングの書籍は、日本語で出版されている2冊の本があります。
エッセンシャル版書籍『ダブル・ゴール・コーチングの持つパワー』

序文 フィル・ジャクソン
第1章:コーチとして次の世代に引き継ぐもの
第2章:ダブル・ゴール・コーチ®
第3章:熟達達成のためのELMツリーを用いたコーチング
第4章:熟達達成のためのELMツリー実践ツールキット
第5章:スポーツ選手の感情タンク
第6章:感情タンク実践ツールキット
第7章:スポーツマンシップの先にあるもの:試合への敬意
第8章:試合への敬意の実践ツールキット
第9章:ダブル・ゴール・コーチのためのケーススタディ(10選)
第10章:コーチとして次の世代に引き継ぐものを再考する
本格版書籍『ダブル・ゴール・コーチ(東洋館出版社)』

元ラグビー日本代表主将、廣瀬俊朗氏絶賛! 。勝つことを目指しつつ、スポーツを通じて人生の教訓や健やかな人格形成のために必要なことを教えるために、何をどうすればよいのかを解説する。全米で絶賛されたユーススポーツコーチングの教科書、待望の邦訳!
子どもの頃に始めたスポーツ。大好きだったその競技を、親やコーチの厳しい指導に嫌気がさして辞めてしまう子がいる。あまりにも勝利を優先させるコーチの指導は、ときとして子どもにその競技そのものを嫌いにさせてしまうことがある。それはあまりにも悲しい出来事だ。
一方で、コーチの指導法一つで、スポーツだけでなく人生においても大きな糧になる素晴らしい体験もできる。本書はスポーツのみならず、人生の勝者を育てるためにはどうすればいいのかを詳述した本である。
ユーススポーツにおける課題に関する書籍『スポーツの世界から暴力をなくす30の方法』

バレーが嫌いだったけれど、バレーがなければ成長できなかった。だからこそスポーツを本気で変えたい。暴力暴言なしでも絶対強くなれる。「監督が怒ってはいけない大会」代表理事・益子直美)
ーーーーー
数えきれないほど叩かれました。
集合の際に呼ばれて、みんなの目の前で顔を。
血が出てたんですけれど、監督が殴るのは止まらなかった……
(ヒューマン・ライツ・ウォッチのアンケートから)
・殴る、はたく、蹴る、物でたたく
・過剰な食事の強要、水や食事の制限
・罰としての行き過ぎたトレーニング
・罰としての短髪、坊主頭
・上級生からの暴力·暴言
・性虐待
・暴言
暴力は、一種の指導方法として日本のスポーツ界に深く根付いている。
日本の悪しき危険な慣習をなくし、子どもの権利・安全・健康をまもる社会のしくみ・方法を、子どものスポーツ指導に関わる第一線の執筆陣が提案します。










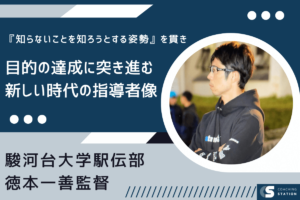



コメントを残す